冬になると読みたくなる、不朽の名作。
基本情報
| 訳 | 内田 莉莎子(うちだ りさこ) |
| 絵 | エウゲーニ・M・ラチョフ |
| 出版社 | 福音館書店 |
| おすすめ年齢 | 3歳~ |
| 初版 | 1965年 11月 1日 |

なんだか心も温まる絵本だね~
あらすじ
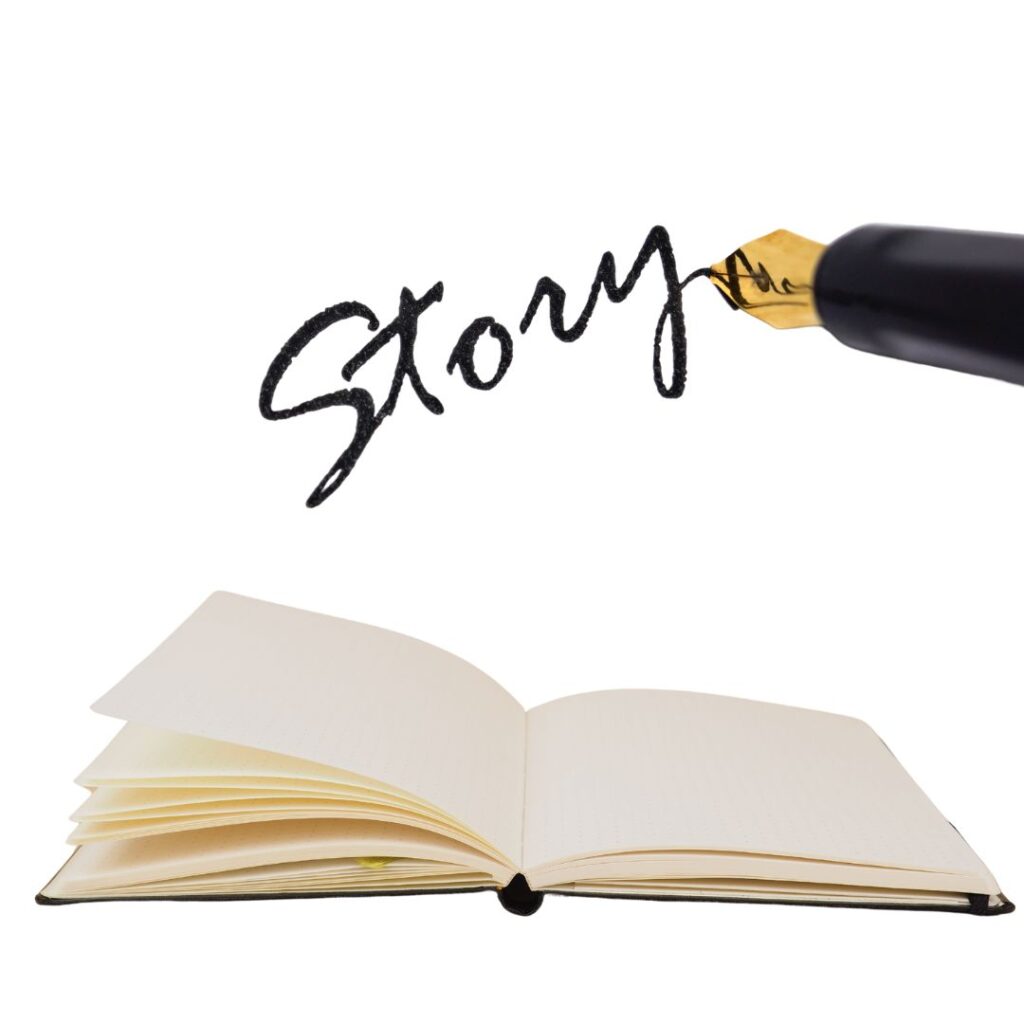
動物がみんなで入って、手袋の中は満員!
おじいさんが森の中に手袋を片方落としてしまいます。雪の上に落ちていた手袋にネズミが住みこみました。そこへ、カエルやウサギやキツネが次つぎやってきて、「わたしもいれて」「ぼくもいれて」と仲間入り。手袋はその度に少しずつ大きくなっていき、今にもはじけそう……。最後には大きなクマまでやって来ましたよ。手袋の中はもう満員! そこにおじいさんが手袋を探しにもどってきました。さあ、いったいどうなるのでしょうか?
私がこの本を選んだ理由
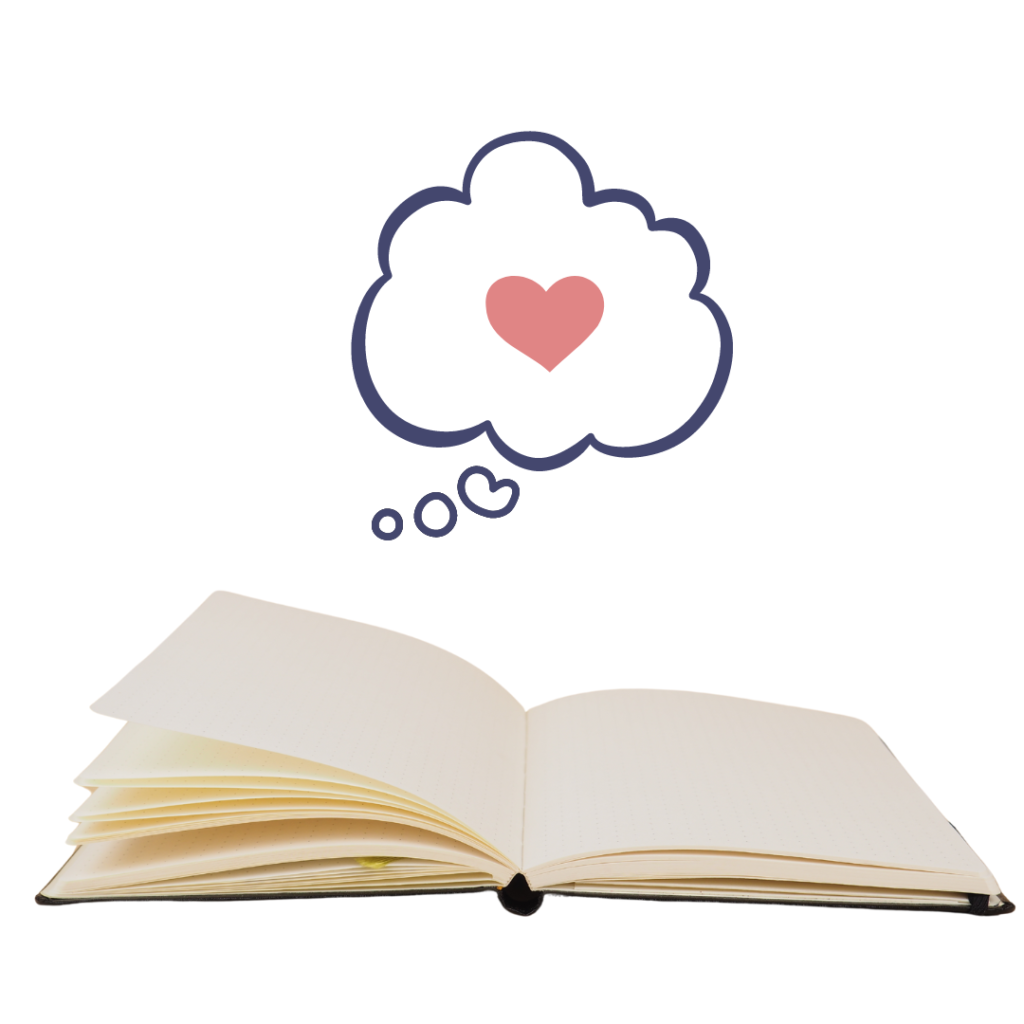
口から出やすい言葉
「だれだ、てぶくろに すんでいるのは?」
「くいしんぼねずみと ぴょんぴょんがえると はやあしうさぎと おしゃれぎつねと はいいろおおかみと きばもちいのしし あなたは?」
— 絵本「てぶくろ」
この場目も、非常に長いセリフが含まれていますが、耳にスッと入ってくるような不思議なリズムがありますね。
子どもも、読み聞かせに慣れていない大人も、自然とスラスラ言える文章の絵本です。これは、絵本の大切な要素でもあります。このようにてぶくろは、文章が秀逸な絵本の1つと言えます。

良い絵本は、読みやすい!
効果的な描写
冷静に考えると、イノシシが手袋に入るなんてあり得ない事です。でも、絵本を通してみると不思議と違和感がないのです。
この物語は、もともとウクライナの民話です。素話をする上ではある程度のファンタジーも許容されやすいですが、それを絵にしてしまうと無理やり感が出て、子ども達が違和感を感じてしまう要因の1つになりかねません。これが昔話の絵本化が難しい要因の1つでもあります。
ですが、この絵本は、
- 1つの動物が来る事に、手袋を描く方向を切り替える(構図の変化)
- 少しずつ、手袋をリフォーム工事していく様子を描く(虚構の世界へ入りやすい仕掛け)
という2つの工夫によって、子ども達に「本当にあり得そう」と思わせる魅力を持ち合わせているのだと思います。
手袋に、いきなり「イノシシが入りました」というのでは「嘘だ。あり得ない。」と思うけれど、小さな動物から始まり、だんだん大きな動物が入ってくる過程の中で、その絵が効果的に描写される事によって読み手にとって本当の話になっていくのだと思います。
むしろ、嘘の話を絵が本当にするような感覚の天才的な描写力です。

ずっと同じ場面で繰り広げられる物語なのに、退屈しないね!
手袋の中に”生活”がある
作中に登場する手袋は、ウサギが入ったあとから”家化”していきます。現実的にも無理がある動物あたりから虚構の世界に変化するこの繊細な構成が本当によく考えられた絵本だなと思います。
また、手袋には煙突が取り付けられ、そこから小さい煙が上がり始めます。物語が進むにつれてその煙の量は少しずつ増えて、中の生活を想像させます。もしかしたら暖炉で温まっているのかも知れないし、料理を作っているのかも知れない。中のあたたかな様子をこの煙突で表現しているように思います。
ですが、一貫して中の様子を見る事は出来ません。この隠された部分こそが子ども達の想像の余地であり、空想の可能性だと思います。実際、園の子ども達も手袋の中の様子を想像しては話をしてくれます。
また、はじめにネズミが「ここで暮らす事にするわ」と発言します。このセリフが子ども達に生活を想像させる重要な一言であるように思います。

皆を受け入れていく、仲良しの動物たち!その優しさが尊い!
のっそりぐまはどう入る?
最後に熊が手袋に入りますが、実は熊が入った後の様子は絵として描かれえていません。
1匹の動物が暮らす(増える)ごとに、1つの工夫がされてきたこの絵本ですが、熊が入った後にはどのような手袋になったのでしょうか?
ここを描き切らずに、子ども達に手渡されています。皆さんならどんな手袋を想像しますか?

ほんの端っこってどこだろう・・・?笑
寒さを伝える”絵”
この物語が寒い日だという事は、文章の中では語られていません。
しかし、しんしんと雪が降り体が心から冷えるような寒い日である事は、絵がよく語ってくれています。深く吸い込まれるような、暗めの背景描写がその寒さをよく表現してくれていますね。
この寒さが絵で語られる事で、動物たちの持つ優しさ(心の温かさ)、そして手袋の中の温かさが強調されていくのではないでしょうか。この対比があるからこそ、このもの語りの持つあたたさが心に残るのだと思います。

見れば見るほど引き込まれる!美しい背景にも注目してね♪
もとに戻る。
最後のページには、一番初めに描かれたものと同じ手袋が小さく描かれています。
おじいさんにとっては、何事もなかったかのようにあっけなく物語は終わっていきます。子ども達はここで空想の世界から、現実の世界に戻ってきます。
そして、雪の積もり方を見てみても、まったく時間が経過していないように思えます。しかし動物たちが次々と入ってきたその時間経過はきっと子ども一人ひとりは違う風にとらえています。
ほんの一瞬の空想の出来事だったのか、それとも1時間程度の物語だったのか。はたまた、1週間くらいのスケールだったのか。どんな解釈にも合う良いラストだなと個人的には思います。

同じ絵だけど手袋に対する印象は、最初と最後で全然違うね!




コメント