約60年、子ども達に愛され続けた『かばくん』のゆったりとした一日。
サンケイ児童出版文化賞推薦
全国学校図書館協議会選定
厚生省中央児童福祉審議会推薦
基本情報
| 作 | 岸田 衿子 |
| 絵 | 中谷千代子 |
| 出版社 | 福音館書店 |
| 初版 | 1966年12月 |
| おすすめ年齢 | 3歳~ |
あらすじ

動物園のかばの1日を生き生きと描いた絵本
動物園に朝が来ました。かばの親子のところに、かめくんを連れた男の子がやってきます。「おきてくれかばくん」。水からあがったがかばくんが姿を現すと、動物園に来ていた子どもたちはびっくり。やがてご飯の時間、かばくんはキャベツをまるごと一口でぱくり。食べた後はごろんところがっておやすみなさい……。シンプルで詩的な文章と、ゆったりとした油絵が、大きくてユーモラスなかばの姿を生き生きと描きます。
私がこの本を選んだ理由
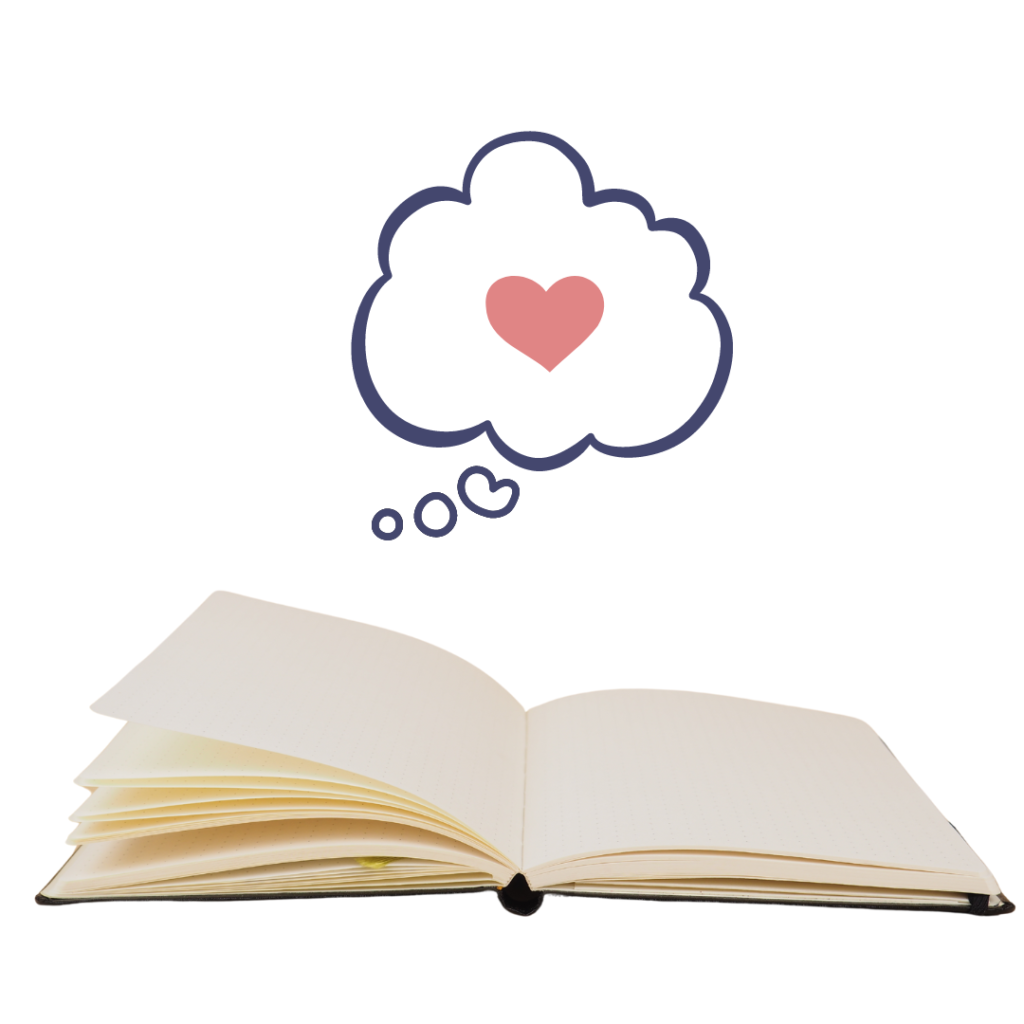
世界に認められた絵本(ペールカストールのアルバムの1冊!)
ペール・カストールとは、フランスの童話コレクションです。
日本における福音館の「こどものとも」のモデルになったとも言われており、教育活動家のポール・フォシェが自らを「ペール・カストール(=ビーバーおじさん)」と名乗り、子ども達に語りかけていた事から、このコレクションはペールカストールと呼ばれているそうです。
そのポール・フォシェはこの絵本の詩を「俳句ですね、面白い」と評価し、次に絵を「油絵だけど、ヨーロッパの人間はこんな線を描かない。これは浮世絵、日本人の絵だ」と言ったそうです。
そして、翻訳本を出さない事で有名なフォシェさんが、この本を珍しい翻訳本としてペール・カストールのアルバムに追加したのです。
参考:シリーズ・松井直の世界2 松井直と『こどものとも』創刊から149号まで
まさに、世界に認められた日本の絵本の1つ! 日本を代表する名作です!

テキストも絵も最上級!
油絵での力強い表現
油絵はお金もかかるし、体力を使うし、描くのが難しいのであまり絵本に使われる事はありませんが、この絵本は体の大きな『かばくん』をダイナミックな油絵がよく表現しています。
また、『かばくん』を描く為に中谷さんが実際に動物園に取材に行った際、以下のような出来事があったんだとか
「『かばくん』の時には上野の動物園が(取材先の)主で。中谷さんがかばに会いに行くと、本当にかばが水の中にいて、鼻の先と目のところしか見えないんですって。それで、ずーっと待ってたら、お客さんの男の子が、『おきてくれ かばくん』って本当に言ったって言うの。テキストと同じようにね。自分もちょうどそう言いたかったから、びっくりしたって。

一切の妥協なく、ダイナミックに描かれた素晴らしい絵です!
詩的なテキスト
『かばくん』は先にテキストがあり、後から絵が加えられた絵本です。
『どうぶつの12ヵ月』という歌を岸田さんが作詞をし、その7月に登場するのが『かばくん』だったそうです。その歌詞を絵本にする事になって中谷さんと山小屋で色々相談をして生まれたのがこのかばくんだそうです。
この絵本のテキストの文だけを声に出して読んでみると、これがただの文ではなく、詩である事に気が付けると思います。
ユーモラスで、美しく、リズミカルな文は声に出して届けられると、その良さがよりつたわっていくものです。
いろいろな絵本があっていいのだけれど、お話っていうと意味性を持つようになりますよね。それよりも音、日本語のリズム性、そういうもので楽しくできればいいと思う。

詩的な文を味わいつくそう!




コメント