いつも研修にご参加いただきありがとうございます。皆さんにとってより良い学びの場が提供出来たらと思い、Q&Aページを作成してみました。よくある質問をまとめていますので参考にされてみてください。
乳児保育
食事について
体調、前日夜や朝の食事内容、睡眠の質、午前中の遊びの内容などによって、子どもの姿は変わります。

そのためその日その日の子どもの姿や何時に朝ご飯を食べてきたという「時間」に細やかに合わせすぎると、園の中での子ども自身の日課もつくられにくくなるのかも…
お腹が空いている姿であれば手立てで姿が変わることもありますし、もちろんクラス全体の日課と個人の日課があっていないという場合もあります。 こどものとも社オンライン園内研修の「食事の悩み・課題」編で、様々な手立てを紹介していますので、よろしければご覧頂き、1つずつ手立てを試されてみてください。
※ 動画は3月末まで何度も視聴できますので、クラス担任の皆さんで共通理解を深めていくと、よりクラス全体の日課がスムーズに流れるようになってくると思います。
流れる日課は、毎日の生活が規則的にくりかえされることで、少しずつ次の出来事がわかるようになります。次に自分がどのような行為をするのか、自分の順番がいつまわってくるのかがわかるようになります。その結果、子どもに安心感やお部屋の落ち着いた雰囲気をもたらします。
年度のはじめであれば、子どもが見通しがもてていないのは自然な姿です。年度のはじめにそのことを大人が理解したうえでの子どもへの配慮が求められます。順番を変える必要性のある子もいるかもしれませんが、オンラインの手立てをご参考に、本当に順番を変える必要性があるのかをクラスで話し合われてみてください。
原則としては、お腹が空いている姿に応じて頻繁に順番を変えると、子どもは見通しがもてなくなるため、安心して遊んで待つことが難しくなるなど、子どもが主体性に生活する流れる日課ではなく、結果的に大人が流す日課になる傾向があります。
子どもの24時間の生活リズムを把握し、お腹が空く時間帯を平均値化し、順番を決めてみてください。
保護者の方のお仕事が変則的な労働時間により、こどもの日課が定まりにくい場合は概ね2パターンの日課を考えることや、保護者の方に生活習慣の重要性や情報を共有し、だいたい同じ時間帯に朝食が摂れないか相談するのもひとつの手立てです。
保護者の方には強制ではなく、それぞれの家庭の状況や気持ちに寄り添い、納得して引き受けていただけることを大事にされてください。
着脱について
排泄について
◎大人が減るとトラブルが増えるのはなぜだろう?
育児担当制で一人ひとりを大切に育てるための条件を整理すると、【子どもが自分のまわりの道具(玩具)を使って自らあそべる環境をつくる】ことが前提の1つになります。
本来であれば、乳児期の子どもは集団で楽しくあそぶという発達段階ではありませんが、園・クラスという集団の空間で1日を過ごすことになります。
そのことを念頭に保育室を構成することが求められます。

やっぱりポイントの1つは遊びなんだね~
◎自ら遊ぶ主体となる為に…
乳児期は一人ひとりの子どもが安心感・安全感を持って情緒が安定することで、自らあそぶ主体になれます。 だからこそ1対1の育児行為の時間が大切になります。

子どもはまわりの環境に関わりながら、その時々の興味関心・発達課題にあわせてあそびながら成長していきます。
身体全体の機能を使って運動して、まわりのモノや作用を探索して、それらを操作しながら微細の機能を働かせていき、やがては見立てて意図的に構成構造したり、役を演じて社会を再現していくようになります。
◎遊びの観点
今回から3回にわたり、「あそびの観点」から手立てをご紹介します。
お部屋にいる子どものあそびの環境が豊かになることで、結果としてトラブルが減り、1対1の育児行為の時間もさらに充実してくると思います。
□あそび道具が発達にあっていますか?
⇒発達にあっていないあそび道具は、難しすぎると大人なしでは遊べませんし、簡単すぎるとあそびのモチベーションが生まれません。 1人ひとりの子どもの姿をみてそこにどんな「あそび」や「あそび道具」を用意したらよいのか、話し合われてみてください。
参考資料:吉本和子著「乳児保育P132」

あそびが発達に合っているかは、子ども達の姿からも読み取れるんだね!
□数は足りていますか?
⇒乳児期の子どもの発達段階から考慮すると、まだ気持ちよくモノの貸し借りができる時期ではありません。 遊び道具が1個や少量しかないのは、子どもたちにとって「そのおもちゃを取りあいなさい」というシビアなメッセージになります。遊び道具の量も大切です。
概ねの目安はカゴいっぱい入る分であると、2~4人の子どもが遊ぶことができる量になります。 気持ちよく自己決定して貸し借りが出来るようになるのは個人差がありますが、概ね2歳児クラスの終わり頃です。
それまでは、一人で満足できる量と空間の保障の工夫が必要になります。

環境構成で、不要なトラブルも減らせるんだな~
日課について
◎眠気のメカニズム
眠気は脳内にある多くのタンパク質のリン酸化という生理的メカニズムによって起こるため、人は眠い時は空腹感を感じず、睡眠欲求がもっとも優先されます。
もし眠たい子を無理に目覚めさせながら食事をさせても、噛む力・回数が減りますし、消化吸収する力もおちます。 機嫌よく食事にも向かえないため、まずは睡眠欲求を満たす必要があります。
◎手立ての例
眠たくて、寝てしまう状況であれば、睡眠を優先し、食事の順番を後半や最後にされてみてください。 個人差もありますが目安としては睡眠のワンサイクルを目安に35~40分で、子ども自身が心地よく目覚められる環境づくりを大切にすると良いと思います。
- お布団の足元をめくり、涼しくしてみる。
- 部屋を明るくしてみる、
- 気持ちよい季節であれば窓を開けてみる。
など、自分が寝ていて、起こされるときどんな風にしてくれたら心地よく目覚められるかな?というのもひとつの指標だと思います。
◎おおむねの日課の変化
眠気で機嫌が悪くなったり、眠たそうな時は寝る、という日課の柔軟な幅をもたせる時期が変則2回寝の時期です。
↓
0・1歳児クラスは、2回寝、変則2回寝の子と1回寝の子がいるため、年度はじめに計画した食事の順番が年度途中で変化する子も中にはいます。
↓
秋頃にはおおよその子どもが1回寝になっていきますので、それまでは、その子自身が成長と共に1回寝になっていけるような環境づくりと配慮を大切にされてみてください。
日課表は、園という集団生活の中で、一人ひとりの子どもの生活リズムを保障するために、クラスの保育者がどのように保育をしたらよいのか、どのような連携や助け合いが必要かを知るためにあります。

※連携とは「同じ目的をもつ者が協力しあうこと」です
◎乳児期は人生で一番成長が著しい時期であり、また個人差がある時期!
例えば、午前11時30分の時間帯という同じ空間の中に、食事をしている子、寝ている子、遊んでいる子がいる状況が日常の光景になります。
つまり、一人ひとりの生体リズムや生活リズムがそれぞれ違う子ども達がいる環境です。 そのような時期の子ども達が過ごすクラスでは、クラスのスケジュールに合わせるのではなく、 一人ひとりの日課をクラスのなかで流れるように構成する必要性があります。
◎日課表は大人にとっても必要なツール
一人ひとりの日課をクラスのなかで流れるように構成するには、円滑な連携をはかりながら、全体の日課を進めていくことが、クラスの保育者に求められます。 自分自身の1日の流れだけでなく、クラスの他の保育者が今何をしているのかを知ることができるのが日課表です。また、自分がお休みの日に担当をしてくれる保育者に対しても必要なものになります。

以前のわかたけ保育園の経験談として、日課表をつくりあげたことに満足して、クラスで日課表が機能しなかったことがあります💦
◎都度日課表を作るべきか?
前置きが少し長くなりましたが、 「都度日課表を作成することが必要?」という質問ですが、クラスのみんなが流れる日課の重要性を理解し、作成して、実践し、一人ひとりの生活リズムを保障し、みんなで助け合いや連携がとれるようになったら目的は果たされるので、別の形で情報の共有を進めていくよいと思います。
◎食事の時間を例に考えると…
例えば、食事であれば1対1から1対2になったら助け合いや連携も変わっていきます。 引き続き同じように日課表を作成した方がクラスの連携が取りやすいのであれば、それもよいと思いますし、「ここは自分たちでもう大丈夫だよね」という状況であれば、変化したことを共有していくとよいと思います。

「子どもの成長と共に何の情報を共有していったら連携がとれるのか」が1つの大事な観点だと思います。
◎尊い時間を積み重ねる為に
最後に、佐々木正美さんの著書のなかで紹介されている言葉を分ちあわせてください。
一人ひとりの子どもとの尊い時間を積み重ねることができるのが、流れる日課です。 そういった時間がつくれる日課表は、私たちにとってとても心強い味方です。
「人生は『はじめよければすべてよし』といってもいいくらいです。 乳児期のスタートがよければ、貧しく育っても健康に幸福に生きていける。悪事を働いたりなんてしない。黙々と、コツコツと、人生をまっとうできるようになっていきます。
大きくなってからつまずいても、回復は早いですよ。 いっぽう、最初のつまずきがあると、人生はこうも困難になるのかというほど、問題が起こります。人生を左右するほどの違いが、乳児期のすごしかたにあるわけです。」
佐々木正美著「あなたは人生に感謝ができますか? エリクソンの心理学に教えられた『幸せな生き方の道すじ』」
◎結論
前回の内容を踏まえたうえで、日課表を作成し直す必要性を感じるときは作成されてよいと思いますし、クラスの保育者みんなが状況を把握できて見通しがもてていたら作成されなくても大丈夫だと思います。

園の状況に応じてケースバイケースですね~
◎日課を見直す際に気を付けたい事
年度初めに日課表を作成できたら、実際の保育の中で子どもの姿を観察し、振り返りながらクラスで一貫して進めることで、クラスの日課が定着していきます。 ご質問の中にもあるように、日課表は決めたものが一年間ずっと続くのではなく、子どもの成長と共に変化していきます。
ただし、大人の都合で日課をかえたり、子どものそのときの姿に応じて頻繁に順番をかえると子どもが見通しをもちにくくなり、子どもが主体的に生活することが難しくなります。

子どもの成長と共に変化していく事が大切なんですね~
◎年間計画の存在
そのため育児の年間計画をもとに大人が1年間の見通しをもつことで、子どものおおよその1年間の成長・発達が見えてきますし、できる限り順番がかわらない(日課がかわらない)ように工夫できるなど、より丁寧な育児が深まっていくと感じています。
0・1歳児クラスは変則2回寝の子と1回寝の子がいるため、年度はじめの食事の順番が年度途中で変化していく子もいます。年間計画によって1年間の見通しをもちながら保育を行うことで、子どもの姿に応じて都度日課表を作り直すことはなくなると思います。
1歳児クラスであれば、「夏頃までは水遊び等もあり、特に体力を使うので早く眠くなるけど、秋頃には体力がついてリズムが定着してくるな」というように担任全員で見通しがもてていると、クラス全体のおおらかで安心感のある雰囲気がつくられやすくなると思います。


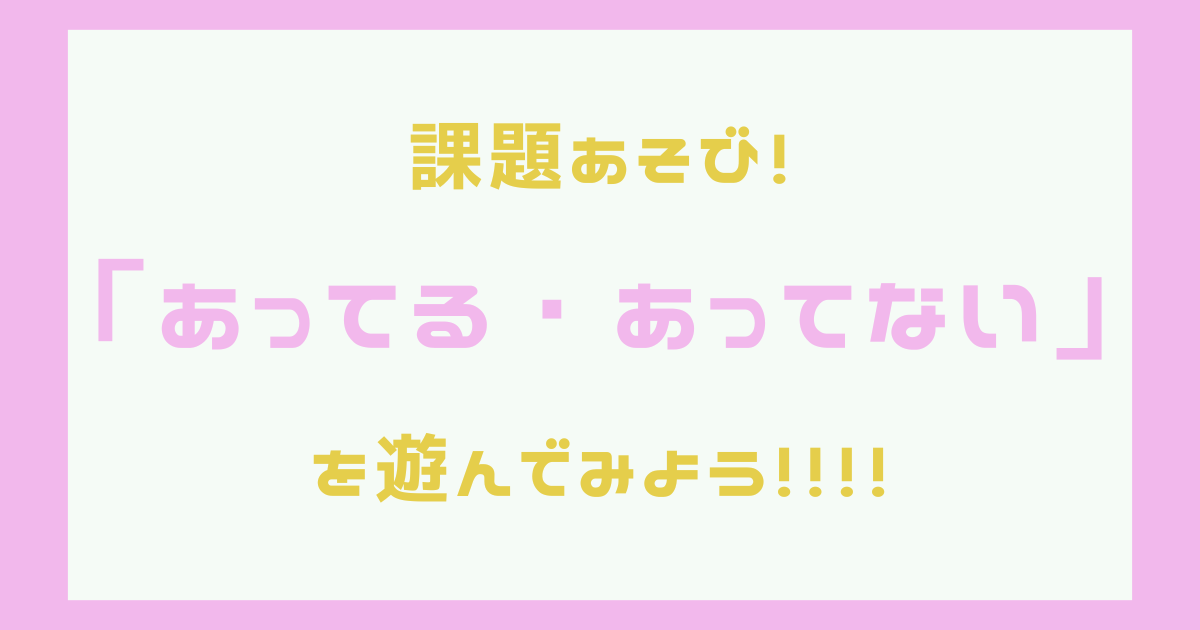

コメント