“てんかん”を持つ人は、100名に1人くらいの割合でいると言われています。
こう聞くと、意外と身近なんだな~と思いませんか?
特に”てんかん”は3歳を超えてからも新たに発症するケースがある為、この病気について正しく理解しておく事は、乳児クラスの保育士さんはもちろん、幼児クラスの保育士さんにとっても非常に大切な事だと思います。
そこで今回は、意外と身近な”てんかん”についての基本的な事項と保育上の留意点について確認していこうと思います♪ぜひ最後までお付き合いください!
基本的な事項の確認

まずは”てんかん”について医療的な定義を簡単に確認しておきたいと思います。
(医療的観点を含むため今回は”障害”という漢字を使用します。)
①転換は、脳の神経細胞の過剰放電による反復性の発作を主な特徴とする障害です。
②てんかんの原因は様々です。脳梗塞や髄膜炎などの場合もありますが、原因不明のてんかんも今だに多くあります。つまり、原因については完全には解明されていないのです。
③原因は不明ですが、遺伝性はないと言われています。
④主な症状は発作です。発作は短時間に経過する身体的、あるいは精神的な症状です。
⑤意識喪失を伴う場合と、そうでない場合の両方があります。
保育現場でよく聞く”てんかん”2選!
保育現場で特に覚えておく必要があるのは、乳児期にも認められる点頭てんかんと、幼児期に発症する事が多いレノックス症候群の2つです。以下に1つずつ説明していきますね。
店頭てんかん
ウエスト症候群という名前で呼ばれる事もあります。
乳児期(4~9か月)にも認められ、発作型の多くは、屈曲型の短い全身性強直発作です。これは、両上肢(両手)を広げて上げて頭部を前屈、体幹を屈曲する数秒の短い発作で下肢(下半身)も股関節・膝関節で屈曲する姿勢が最も多くみられます。てんかんの様子をyoutubeで紹介して下さっている方がいらっしゃいましたので共有しておきますね。
保育士さんには一見して欲しい動画ですが、苦手な方はご視聴をお控えください。
モロー反射と少し似ていますが、発作の場合は唐突に、この型を数秒ごとに反復する事が多いです。(=シリーズ形成する事が多い)
モロー反射は、外部からの刺激(光や音などを含む)をキッカケにおこりますが、てんかんは刺激がなくても起こります。
状況としては眠たい時や、うつらうつらとする入眠前に現れる事もあります。その中でも特に起きかけの時に起こる事が多いようです。
また、点頭てんかんの約50%は、この後紹介するレノックス症候群へと移行していきます。
発症と同時に、発達遅延が気付かれる場合も多く、発作を繰り返す事が知的な遅れへと繋がっていく場合もあります。保育士はこのような可能性も十分に踏まえたうえで、今後の発達の様子を見守っていく事が大切になります。
レノックス症候群
レノックス症候群は、3~6歳児に発症する事が多い病です。その約30%は点頭てんかんからの移行だと言われていますが、その他の約70%は新たに発症しています。
今までその予兆がなかった子でも、ある日突然発症する可能性があるという事も知っておく必要があります。
発症型は、多種の小型発作です。中でも、弱い強直発作が多いです。
点頭てんかんと異なる点として、シリーズ形成を示さない(数秒の間に発作を繰り返す訳ではない)場合も多いです。
また、覚醒時や睡眠時などの子どもの状態を問わずに出現する事も特徴の1つです。
保育上の留意点

①発作の持続時間は短いので、発作中の安全を確保して出来るだけ安静に経過を観察する事が大切になります。そして、発作時の様子を出来るだけ細かく医師に伝えましょう。
②発作時は、横向きにして気道を確保する事が大切になります。
③食事中に発作が起きた時には、食べ物を詰まらせないようにすることが大切になります。気道を確保し、口の中に食べ物が残ったままにならないようにします。
④てんかんの基本的な治療は、薬物治療です。発作の程度・始発時刻・誘因・前兆に着目してた観察を作成し、医師に報告する事が出来れば治療は進みやすいです。
⑤発作が終わって意識が戻らないうちに次の発作が起こる場合には専門的処置が必要になります。そのような発作の特徴が確認できるときは、救急車を要請する時に伝えましょう。
環境を見直す事も大切

てんかんは、急に起ります。ジャングルジムの上で発作が起きれば転落してしまうかも知れません。また、倒れた先に机の角などの鋭いものがあれば、ぶつかって大けがをしてしまうかも知れません。
常に子どもの様子をみまもり、保育環境をより安全なものに見直していく努力が大切になります。また、今はてんかんの子がクラスにいなくても「もしてんかんの子がいたら?」とシュミレーションをしながら、生活の導線や先生の配置を考えてみる事定期的にしておいても良いかも知れません。
まとめ
私も、保育園に通う子がある日突然倒れて救急車で運ばれた事があります。医師から「てんかん」の可能性がある。と診断された事を聞いた時はすごく不安になりましたが。
そんな時私たち保育士に出来る事として、
①とにかく子どもの安全を確保する
②状況を正しく把握して医師と共有する
この2点は必ず抑えておきたいポイントとなります。
そして何より、落ち着いて対応する事が大切です。落ち着いた対応をする為にも、正しい知識を持つ事は非常に大切な事なのではないでしょうか。


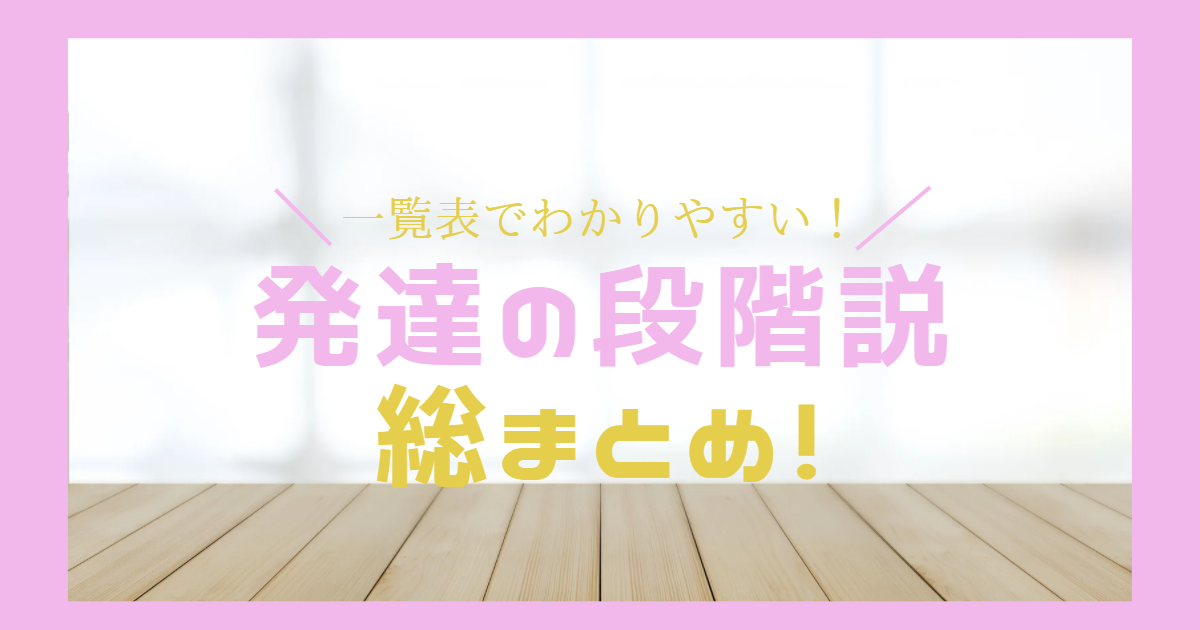

コメント