保育所保育指針の「養護に関する基本的事項」の中に以下の様に記されています。
保育指針に見る情緒の安定

まずは、日本保育の羅針盤!保育指針の文言をチェックしていきましょう♪
情緒の安定
ねらい
① 一人一人の子どもが、安定感をもって過ごせるようにする。
② 一人一人の子どもが、自分の気持ちを安心して表すことができるようにする。
③ 一人一人の子どもが、周囲から主体として受け止められ、主体として育ち、自分を肯定する気持ちが育まれていくようにする。
④ 一人一人の子どもがくつろいで共に過ごし、心身の疲れが癒されるようにする。
内容
① 一人一人の子どもの置かれている状態や発達過程などを的確に把握し、子どもの欲求を適切に満たしながら、応答的な触れ合いや言葉がけを行う。
② 一人一人の子どもの気持ちを受容し、共感しながら、子どもとの継続的な信頼関係を築いていく。
③ 保育士等との信頼関係を基盤に、一人一人の子どもが主体的に活動し、自発性や探索意欲などを高めるとともに、自分への自信をもつことができるよう成長の過程を見守り、適切に働きかける。
④ 一人一人の子どもの生活のリズム、発達過程、保育時間などに応じて、活動内容のバランスや調和を図りながら、適切な食事や休息が取れるようにする。
保育所保育指針には情緒の安定についてこの様に記されています。
引用:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010450&dataType=0&pageNo=1
なぜ情緒の安定が必要なの?
では何故、保育所でそこまで情緒の安定が大切だと言われるのでしょうか。
それは保育所が子どもにとって生活の場だからです。
子どもは保育所で家庭的な雰囲気の中、遊びや生活を営んでいきます。保育者を安全基地として、探索遊びなどを展開していく為にも情緒の安定は欠かせないわけです。
また、情緒の安定は生活習慣の獲得から遊びの展開までまさに生活の全てに関わっています。
情緒の安定、3つのポイント!

では情緒を安定させるためにはどうすれば良いのでしょうか。
子どもの情緒が安定するためには前庭として、保育士との愛着がしっかりと形成されている事が条件となります。
たとえば、保育園で子どもと担当の保育士が何もせずとも自動的に愛着を形成できるかと言えば、そうではないですよね。
もちろん担当制でしっかり関わる事が出来れば、しっかりとアタッチメントを築ける場合が多いですが、そうでない場合も勿論あります。
ではその違いは何なのでしょうか。ポイントは子どもの3つの欲求を満たしてあげられるかどうかです。以下にその3つのポイントについて述べていきます。
①生理的欲求

生理的欲求が満たされている事は、子どもの情緒の安定に大きく影響します。
食事・睡眠・排泄などの基本的な生活な生命の維持と体の成長~心の成長にいたるまで様々な部分において大きな役割を果たしています。
そのため子どもが健康的で気持ちよく過ごすためには「食べる事」や「眠る事」といった生理的な欲求が満たされる必要があるのです。
食事や睡眠など、特に乳児さんは一人ひとりのペースも違うので丁寧に満たしてあげる事が求められます。
②身体的欲求

動きたい欲求は子どもの成長・発達において、とても大切な役割を担っています。
この身体的欲求が満たされている事で子どもは安心して遊びを展開したり生活を営んでいくのです。
発達段階を正確に把握し、今身体にとって必要なあそびを的確に提案していく事は保育士の大きな専門性の1つではないかなと思います。
③知的欲求

知りたいという欲求は子どもにとって大きな喜びにつながるものです。
知的好奇心を満たす仕掛けを多く環境の中に盛り込んで行きましょう。年齢の高い子どもさんであれば対話の中で満たす事も可能かも知れません。
知的欲求を上手に満たすためには環境構成と大人の言葉。この2点を見直してみる事がコツになります。
まとめ
情緒安定のポイントは
- 生理的欲求
- 身体的欲求
- 知的欲求
を上手に満たしていく事でした。
保育を営む上で絶対に欠かせない基本中の基本。それが「情緒の安定」です。しかし、特に年齢が低いと見落としがちなポイントですので、定期的に見直す事も大切かも知れません




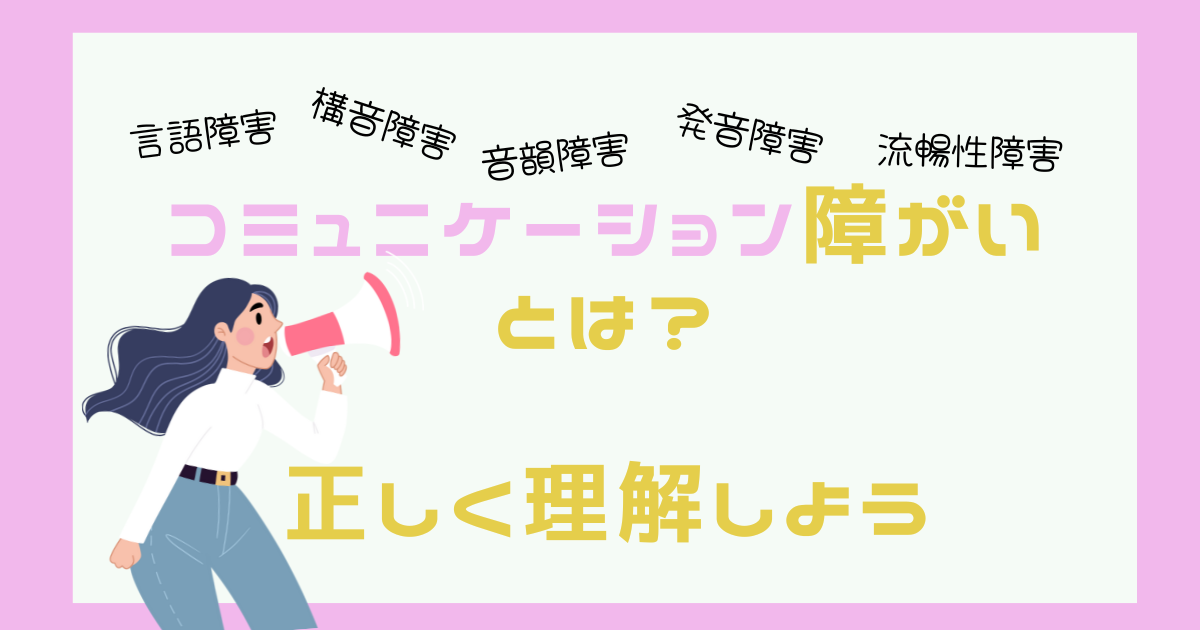
コメント