ボウルビィは、子どもと特定の人との間に結ばれる情緒的な絆を愛着(=アタッチメント)と呼びました。この愛着の形成は保育においても、とても大切な意味を持ってきます。
たとえば保育所保育指針にも、保育士と子どもが情緒的な絆を形成する事の重要性が以下のように記されています。
1 乳児保育に関わるねらい及び内容
(1) 基本的事項
ア 乳児期の発達については、視覚、聴覚などの感覚や、座る、はう、歩くなどの運動機能が著しく発達し、特定の大人との応答的な関わりを通じて、情緒的な絆が形成されるといった特徴がある。これらの発達の特徴を踏まえて、乳児保育は、愛情豊かに、応答的に行われることが特に必要である。
(3) 保育の実施に関わる配慮事項
イ 一人一人の子どもの生育歴の違いに留意しつつ、欲求を適切に満たし、特定の保育士が応答的に関わるように努めること。
愛着行動とは?
愛着段階を確認する前に、愛着行動についても併せて知っておきましょう♪
愛着行動はおおむね以下の3つの種類に分類する事ができます。
- 発信行動(泣く・微笑む・声を出す など)
- 定位行動(後追い・注視・目で追う)
- 能動的身体接触行動(しがみつく・抱きつく・よじ登る)

これらの行動が頻繁に向けられる他者が、その子の愛着対象者だね!
愛着の発達段階
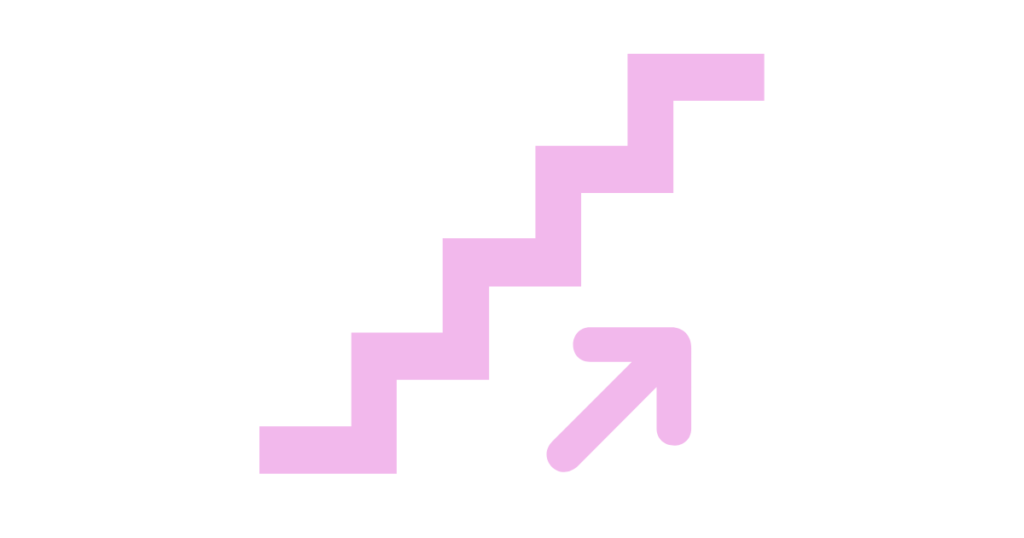
いよいよ愛着の発達段階についてみていきます。ボウルビィは、愛着の発達を以下の4つの段階に分類しています。
| 【前愛着段階】(誕生~2・3か月頃) 人の弁別ができないため、誰に対しても同じように注視・微笑・発声・泣き・掴むなどの愛着行動を示す。 |
| 【愛着形成期】(3か月頃~6か月頃まで) 人の弁別ができてくる為、日常生活でよく関わる大人(母親など)に対して頻繁に微笑や発声を示す。 |
| 【明確な愛着段階】(6か月頃~2・3歳頃まで) 人の弁別がさらに明確になり、特定の人に対する愛着行動が顕著になる。 また、ハイハイや歩行による移動が可能になるため、愛着行動のレパートリーが多様化する。 一方で、見知らぬ人に対する恐れと警戒心が強くなり、人見知りや母子分離不安が生じるようになる。母親を安全基地として母親から情緒的補給を受けながら探索行動に出る。 |
| 【目標修正的協調性の形成】(3歳以上) 愛着対象と自分についての内的ワーキングモデルが安定した形で機能するようになり、愛着対象が近くにいなくても必ず自分のところへ戻ってきてくれる・何かあれば助けてくれるという確信が持てるようになる。 同時に他者の感情や動機を洞察し、相手の行動目的や計画を意識するようになる。 自分の行動を目標に合わせて修正する事ができるようになり協同的な関係が形成される。 |
※参考文献の購入はこちらから↓
具体的な発達の様子

ここからは実際の発達の様子を具体的に見ていきましょう。
生後30日
- 原始反射(モロー反射や把握反射など、脊髄・脳幹が制御する赤ちゃん特有の刺激反応の事)
- 母親の顔・目・声に対する反応と識別
- (生後3~4週間)母親の声に対して優先的にほほ笑む
生後1~3か月
- アイコンタクトをする
- 社会的発声
- 社会的微笑
生後4~6か月
- 母親の声を聴けば落ち着き、ご機嫌になる
- 自然に自分の意志で母に近づく。
- 識別したうえで母親への選択性が高まる
- 母親に対する反応の微調整
生後7~9か月
- 愛着行動はより相手を意識し、その対象は母親に特に集中する
- 分離不安(養育者と一時的に離れる環境に対する不安)
- 人見知り
- 見知らぬ場へ不安を示す。
生後10~15か月
- 母親との好意的な対話がはっきりと定着。
- 声の抑揚、顔の表情など母親を模倣する初期段階。
- 母親の後追い
- より明確に分離不安と母親選択が発現
- 母親からくっついたり離れたりして歩く
- 母親と離れていたあとの際かいに陽性の情緒反応を示す
- 指さしで意思表示をする
生後16か月~2歳
- 自我が芽生え第一次反抗期(=自立期)が始まる
- 首を振ってイヤイヤをする(15~16か月)
- 移行対象の使用(以降対象とは、1~3歳の移行期と呼ばれる時期に肌身離さず持っている客観的な存在の事です。ぬいぐるみや毛布・タオルなどを移行対象として使用する子も多いと思います。それまで、完全に母親に依存し常に欲求が満たされていたために抱いていた全能感(=錯覚)が崩壊し、欲求不満の体験や不安感を持ちます。このとき母親の感覚を思い出させる移行対象に触れることで、幼児は欲求不満や不安を軽減します。つまり移行対象は、分離不安に対する防衛といえます。)
- 分離不安の低減
- 母親がそばにいると、見知らぬ状況や人見知りを制御する
- 遅延模倣(観察した他者の行動を時間をおいてから模倣する事。おままごとなどの遊びは遅延模倣の獲得によって可能になる。)
- 対象の不変性の理解
- 表象を用いる能力(表象とは、頭の中で何かを思い浮かべるお事です)
- 小世界での象徴遊び
生後25か月~3歳
- 慣れ親しんだ環境で母親が戻ってくる保障があれば、母親からの分離に不安なく耐える。
- 人見知りがさらに減弱
- 二語文から三語文へ
- 対象恒常性を維持する(目の前から観察の対象となる人や物が見えなくなっても、今まで見ていたものはどこかに存在するという感覚を持ち続ける事ができる)
- 小世界での遊びと社会的遊び
- 他者との協同の始まり
母親(大人)の接し方

エインズワースの研究によると、母の接し方と子どもの姿には次のような関係性が見られます。

ここでいう母親とは、保育士を含む「身近な大人」の事だと捉えて大丈夫だよ!
子どもの要求に適時対応
子どもは、母を信頼し安心感が得られるのでたやすくいつでも母親から安らぎを得られる。そのため積極的な探索行動ができる。
否定的・統制的な振る舞いが多い
子どもは、母親を安全基地とすることができない
また、母親を避けがちで探索行動も消極的になる。
要求にこたえたり、こたえなかったりと一貫性がない
子どもは安心できず、母親との分離不安が強くなる。時には激しい怒りの感情を見せる。
無秩序的・無法公的に接する
母親が、虐待された経験を持っていたり、気分(感情)障害を持っている場合に多いパターンです。無秩序に接すると、子どもは母親の存在におびえたり、近接や会費という葛藤を示すことが多い。
社会的参照について
子どもは、あいまいな状況や不安な状況では母親の表情や反応を手掛かりに行動します。これは社会的参照と呼ばれる現象です。私も男性保育士なので、特に人見知りされることも多いですが、保護者さんと仲良く話していると、子どもも次第に慣れてくれるパターンが多い気がします。
一般的に、見知らぬ人に会った時に子どもは
▲母親が否定的・防衛的な態度を示すと、拒否や回避などの否定的な反応をみせる事が多いです
〇母親が肯定的な態度をみせると肯定的な反応をすると言われています。

まるで写し鏡だね~
まとめ
愛着の形成は、保育(特に乳児保育)においても大きなポイントです。その発達の様子や段階を知っておくと保育士も見通しが持てていいと思います。
また、愛着関係はもちろん母親以外の特定の大人との間に結ぶ事もできますし、複数の大人と結ぶことができます。これはアタッチメントの形成において大切な事ですので抑えておきたいところです。
ボウルビィのアタッチメント理論を踏まえて明日からも丁寧に保育を展開していきたいですね。





コメント