前回の記事はコチラから↓
『学び』とはなにか?①~2種類の学び方を知る。~ | 保育ふぁん! (hoikufun.com)
学習(=学び)とは、経験によって獲得する行動の変容です。
では、私たちはどのようなメカニズムで新たな行動パターンを獲得していくのでしょうか。
という事で今回は、人間の持つ3つの学び方について学んでいきましょう♪
古典的条件付け(レスポンデント条件付け)
ロシアの生物学者パブロフさんが、犬を使った動物実験をおこないました。その時の結果を基にしているのが、このレスポンデント条件付けです。

実験内容
実験は、犬に聞きなれない音を聞かせた時にどんな反応をするかを観察したものです。
普通の犬ならば、耳をそばたてるなどの反応を示します。
しかし、パブロフは実験で餌と音を一緒に提示する事を何度も繰り返しました。こうする事で、音は餌が出てくる合図である事を学習させようとしたのです。
その結果、最終的に犬は餌が提示されなくても音を聞いただけで唾液を分泌するようになったのです。
消去
この実験では、音と餌を一緒に提示する事をやめてしまえば、音に反応して唾液の分泌量が増える事はなくなっていきます。
これを消去と言います。
このようにレスポンデント条件付けによる学習は消去する事が出来ますが、喜びや恐怖、悲しみ、怒り等といった情動と絡むと、なかなか消去するのが難しくなってしまいます。
これが恐怖症などが発生する仕組みになります。
道具的条件付け(オペラント条件付け)

よく何度も繰り返される行動には、意味があります。スキナーという研究者はネズミとスキナーBOXという装置を使って、オペラント条件付けの実験を行いました。
実験内容
スキナー装置は、レバーを引くと餌がでてくるという装置です。
空腹のねずみさんはたまたまレバーに手が当たって餌が出てくるという行動を何度か経験する中で、餌を手に入れる方法を学んでいきます。すると、これまで行っていた餌を探し回るという行為はへり、レバーを押すという行動が増えます。
レバーを押すという行為が増えたのはその行動によって餌という報酬があったからです。
ある行動に対して、報酬があると、その行動の頻度が増えます。これを強化と言います。
とって欲しい行為があった時に、何か報酬を用意して、行動を促す。これがオペラント条件付けです。例えば幼児教育や育児の場面でもこの”報酬”は、「褒め言葉」等でも同じような結果になります。
観察学習(モデリング)

これまで紹介した条件付けは、体験や経験を基に学ぶという共通点があります。
これに対して、他の人の行動を参考にして学ぶのが観察学習です。
心理学者のバンデューラによれば観察学習は、
- 注意過程
- 保持過程
- 出産過程
- 動機付け過程
の4段階で成っていると述べています。
この事を証明する実験が以下の2つです。
バンデューラの実験①
等身大の人形に対してパンチやキックをする大人の様子を子どもに見せる。そしてその後、玩具や遊具が多数おかれている部屋で子どもに自由遊びをしてもらい、その様子をきろくした。
観察の方法は、
①子どもの目の前で実際に大人が攻撃行動をとっている
②映像として子どもに見せる
③アニメーション映像にして見せる
の3つである。
さぁ、結果はどうなったでしょうか。部屋には、大人が攻撃行動をしていた例の等身大の人形も置いてあります。
すると、攻撃行動を観察した子ども達はいずれの条件においても、攻撃行動を観察しなかった子どもに対して攻撃行動の模倣が多かったとの事です。
バンデューラの実験②
子どもに映像を見せる攻撃行動の結末を2パターン用意し、それぞれの子どもが映像を見た後、どんな行動をとうるのか観察した。
①大人が人形に攻撃行動をとったあと別の大人に罰せられる。
②大人が人形に攻撃行動をとったあと別の大人に褒められる
①の映像を見た子どもは、②の映像をみた子どもより、攻撃行動が少なかった。
実験から分かる事
子どもは経験をしなくても、他者の行動をマネる事で行動のレパートリーを広げていきます。これを代理強化と言います。
この実験からは、観察学習の影響の強さを物語っています。
子どもは、良い事も悪い事も、しっかり真似して行動のレパートリーに追加しようとしますが、どんな行動をほめていくのかで、その行動をとってよいか否かの判断をしっかりと教えていかなければなりませんね。

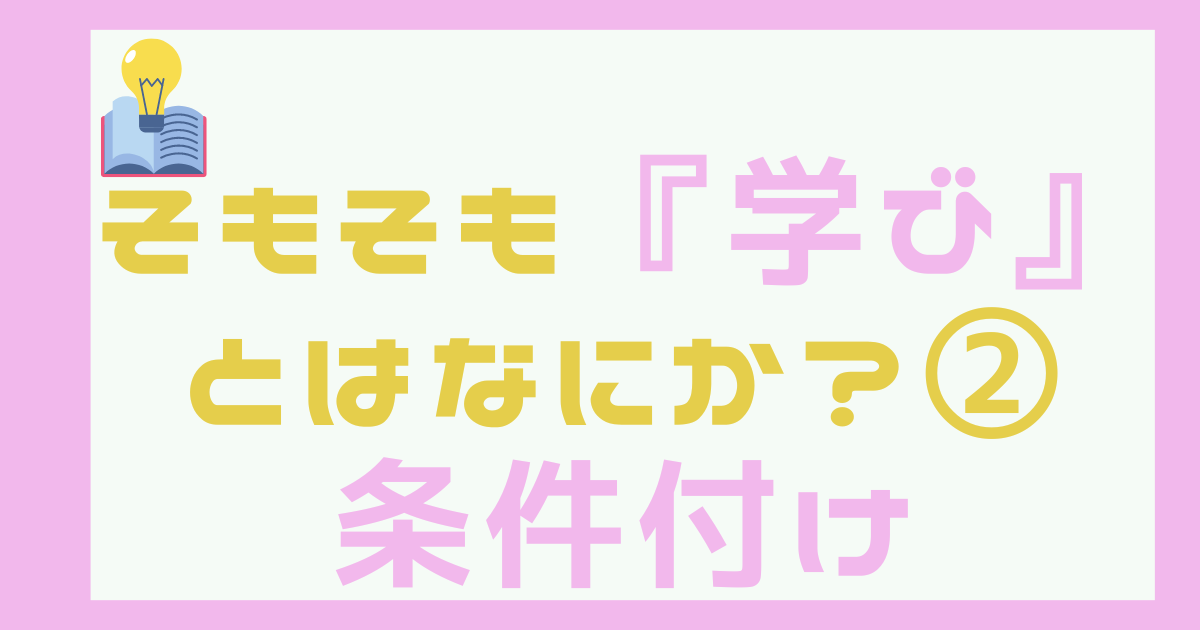
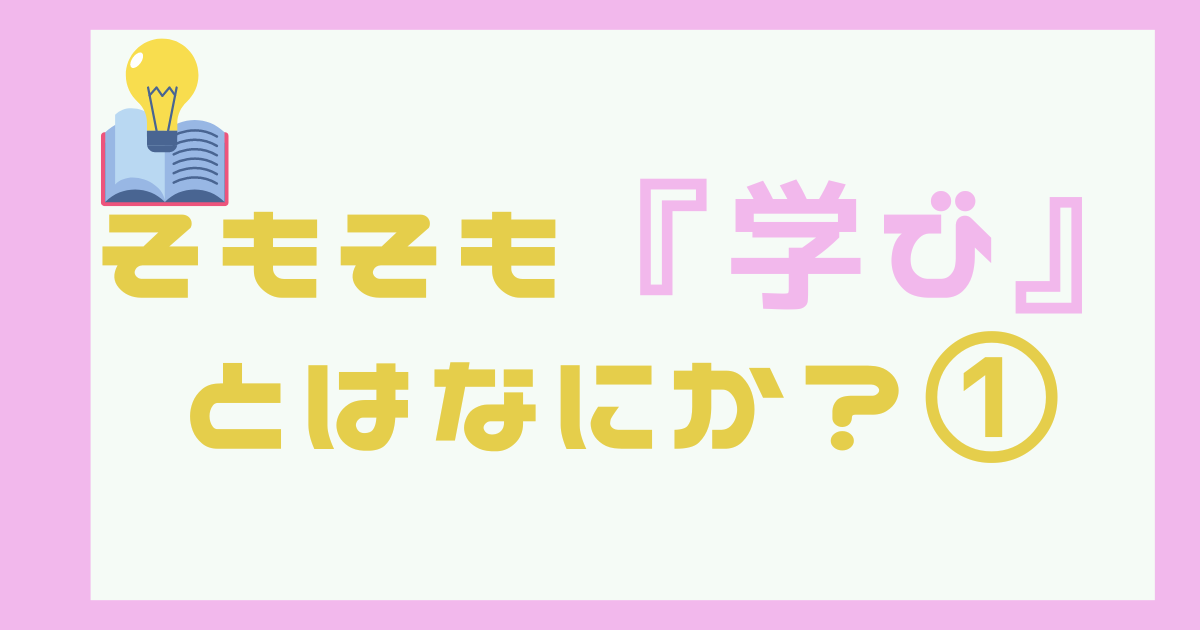
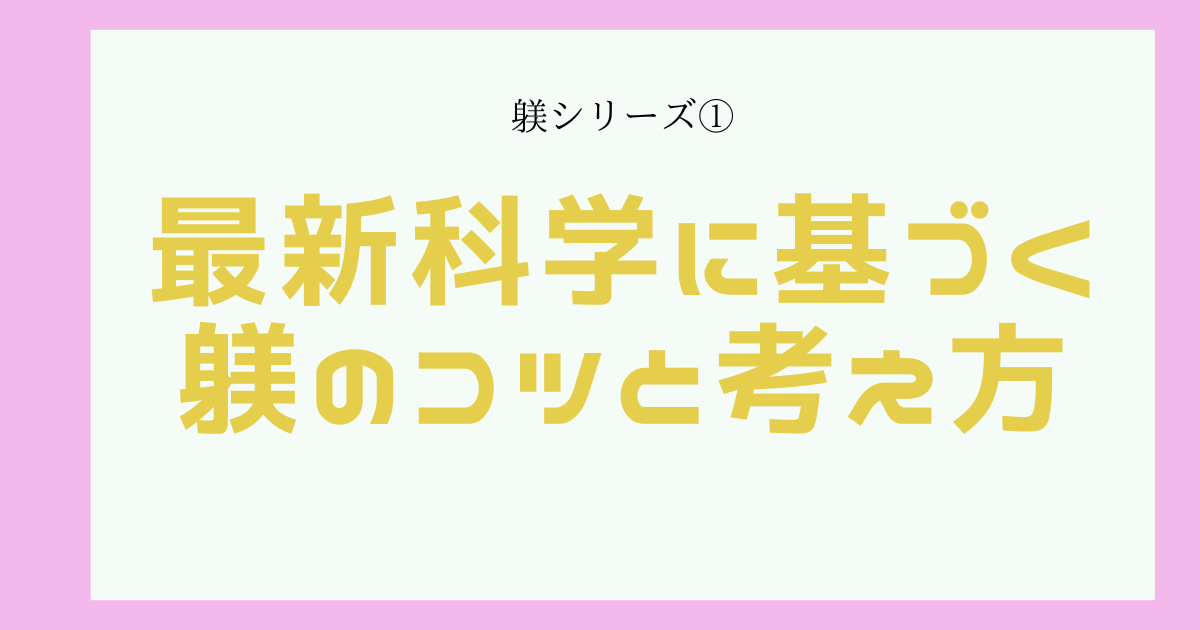
コメント