クラス便りを通じて、各年齢・クラス・発達ごとの特徴や子育てのポイントなどお伝えしてまいりますので、よろしくお願いいたします!今回のクラス便りは最新の科学的知見(主に脳科学)からみた本当に必要な「しつけ」についてです。保育士である私たちも目からうろこの子育てにおけるとても大切な考え方だと思い、全クラス共通版でお配りしたものです。
そもそもの「しつけ」の意味ってなに?
しつけの語源
「しつけ(躾)」と聞くと、「自分勝手なことをしてはいけない」「生活の決まりを身に付ける」などといった社会的規範やモラルなど思い浮かぶことが多いかもしれませんが、根源的な意味としては「人間として社会の中で生きていくために身につけておく必要がある大切なこと」を言います。
「しつけ」という言葉は、もともと「着物をしつける」ということから生まれてきた言葉です。
着物のしつけとは?
着物を縫うときには、いきなり本縫いをするのではなく、本縫いをするときにずれないよう「しつけ糸」をつかって「仮縫い」をします。仮縫いをすることでおおまかにこういう風に縫っていくことがわかり、全体の形がみえてきます。
そして本縫いのときに「しつけ糸」を抜いていきます。
人生にも本縫いの時期がある!!
私たちの中高生の時期のことを思い出してもらいたいのですが、乳幼児期のときに「これはだめ」と親に言いきかされても、思春期になると「何でこんなことしなきゃいけないの?」と自然に疑問がわいてきませんでしたか。
例えば「学校から18時まで帰ってきなさいよ!」と言われて19時に帰ってきたらひどく叱られ、「私はただ友達の相談にのっていただけじゃない。なんで怒られなきゃいけないのよ」と思ったり、「何で自分がやることを親が勝手に決めるのよと」と感じることがでてきたと思います。
実はこの思春期(反抗期)が「本縫い」の時期にあたります。
乳幼児期に社会の中で生きていく上で親から「しつけ糸」として「こうしなさい」とやってきたこと(仮縫い)が、やがて自分で「これが大事だ」「これはやりたくない」と自分でしつけ糸を外して本縫いを始めていく。この期間こそが自分でモラルをつくっていく、自立にむけた人間形成にとても大事なことなのです。
幼児期のしつけ
以上を踏まえて躾について考えていきます。まず、

このようにしつけ糸をあまりに厳しく縫ってしまうと・・・
自信喪失、神経質、傷つきやすい、ひきこもる(依存)など、自分で着物を脱げないような状態に陥りやすくなります。
反対に・・・
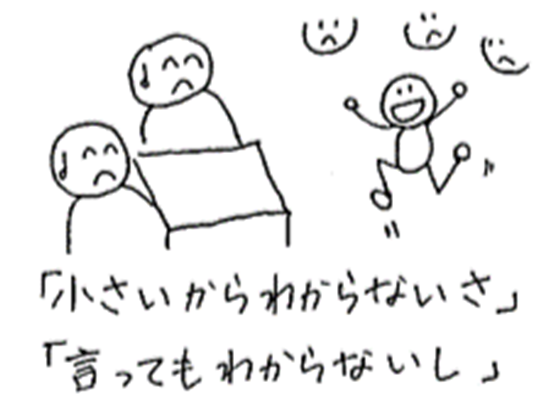
このようにしつけ糸がゆるすぎると・・・
我慢がきかずきれやすい、社会的な不適応感、肥大化した自己などの姿となり本縫いがうまくいきません。
幼児期にしっかりと教えておきたいポイント
さて、躾の意味(目的)をおさえた上で、いよいよ次回の投稿で、科学的知見からのしつけの原則をご紹介したいと思います。原則といっても2つしかありませんが、この2つは子どもの一生を左右する、これだけはしつけとして親しかできない本当に大事な役割ですので、ぜひ実践されてみてください。
詳しくは、次の記事へ。

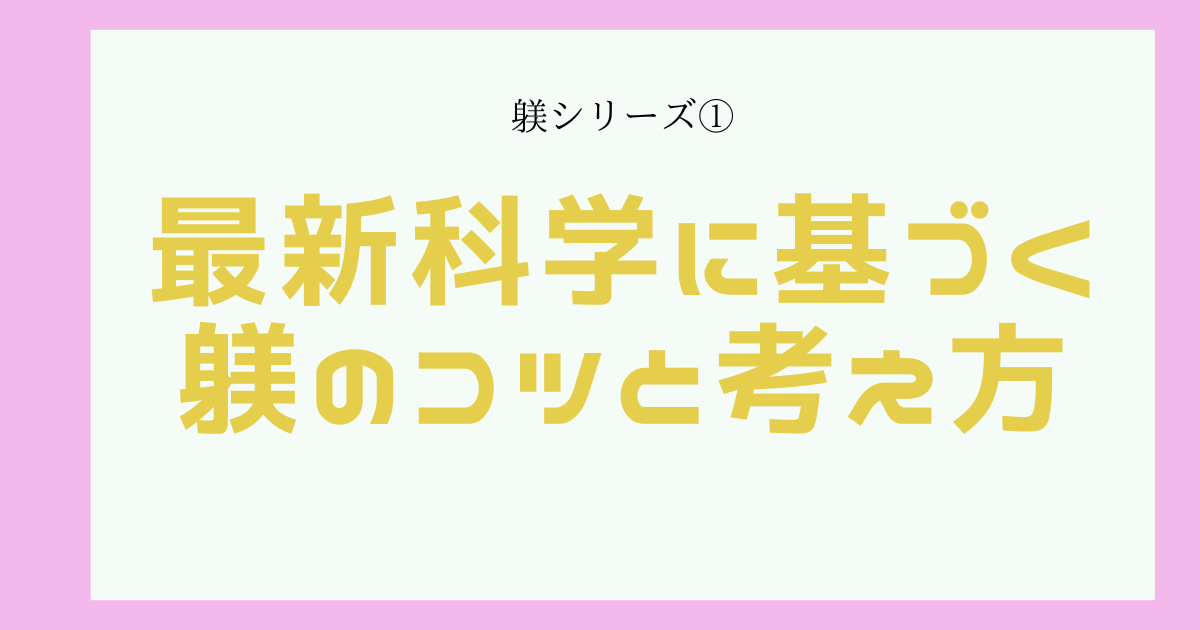
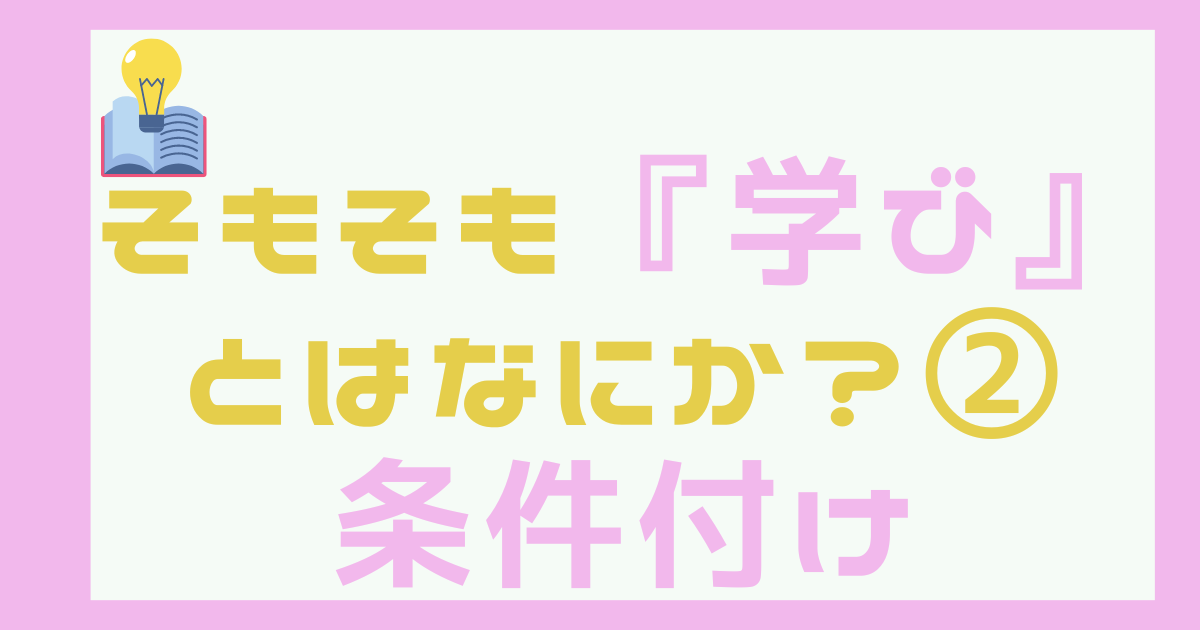
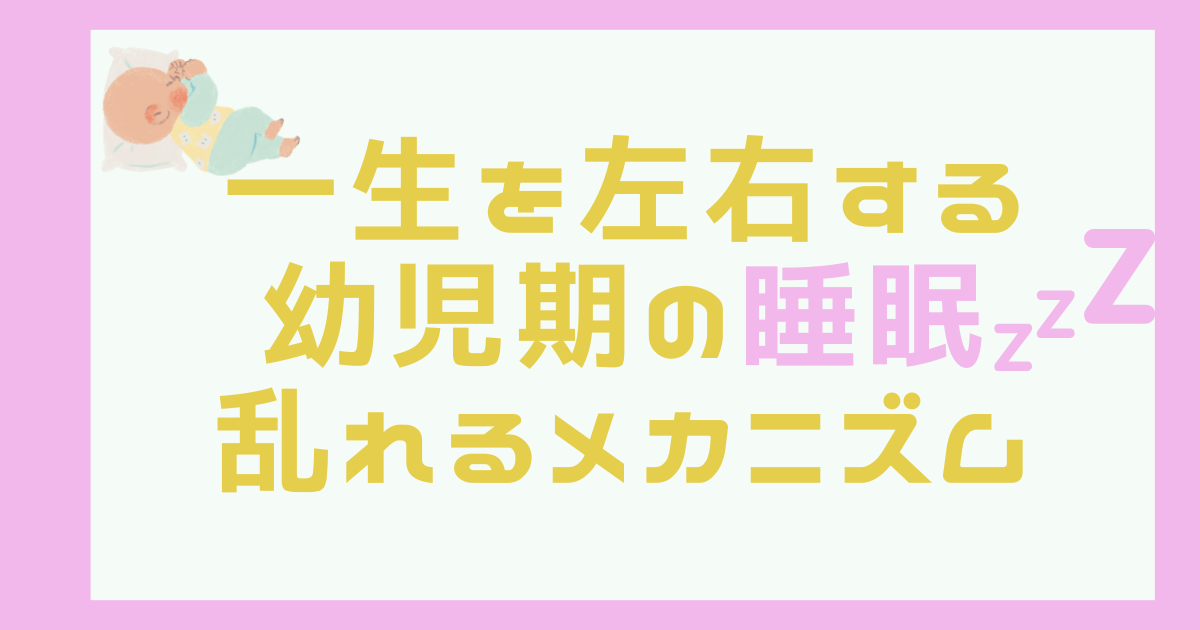
コメント