
様々な著名人が受けたとして注目を集めているモンテッソーリメソッド。
しかし、実際にどんな事をしているのかな、って疑問に思った事のある学生さんや先生も多いと思います。そこで今回は、以下の本を要約して紹介いたします!

今回は出来るだけ箇条書きで情報をまとめ、読みやすくしています!
・モンテッソーリメソッドについて知りたい
・子ども主体の保育をやっていきたい
私が勤めている保育園では、モンテッソーリメソッドに取り組んではいませんが参考になるような情報もたくさんあり、楽しく読み進める事ができました。子ども達が主体的に生活していく為に、明日から取り組めるような具体的な内容がいくつも示されてありました。
本の概要
モンテッソーリメソッドってなに?という疑問をざっくり簡単に理解する事ができる1冊です。
モンテッソーリメソッドを実際に取り入れている園の先生にとっては少し物足りなさを感じる内容かもしれませんが、モンテッソーリメソッドを全く知らない人が入門書として読むには凄くおすすめです!
著者:堀田はるな
出版日:2018年3月7日
ページ数:271P
値段:1100(+税)
出版社:あさ出版
3つの基本
モンテッソーリメソッドでは
- 「何をどのように行うかを自分で決める事」
- 「能力は環境で伸びる事」
を核としています。そしてその中で大切とされているのが以下の3つの基本です。
①自主性を最大限サポート
- 大人はとにかく「環境」を整える
- 助けが必要な時にしっかり関わる
- 好きに気づいて、集中している時は邪魔をしない
- 「教育する」という考えを見直す
- 子どもを観察する
- 学びの主体は子ども
- 努力は好きには勝てない
- 凸凹は当たり前。無理に矯正しない
- 肯定する。受け入れられた子は受け入れる
②生き方の輝度となる体験を提供
- モンテッソーリ教具を使用(日常生活の練習、感覚、数、言語、文化の5つの領域で用意する)
- 失敗は問題解決の練習。直接訂正しすぎない
- 解決策は一緒に考える
- たくさん手を使う
③敏感期に基づく関わり
そもそもモンテッソーリメソッドは24歳までのプログラムが存在する。
その中でも、特に保育士さんが知りたい0~6歳の敏感期は以下の通り!
【秩序の敏感期】2~3歳
【感覚の敏感期】3~6歳
【運動の敏感期】4歳6か月ごろまで
【言語の敏感期】6歳ごろまで
モンテッソーリメソッドではこれらを踏まえて時期に合った環境を用意する事が大切であるとされています。
家庭での環境構成

記事冒頭でも述べていますが、モンテッソーリメソッドでは自分で決める主体性と、環境構成の大切さが核となっています。これらを踏まえて、家庭でもアプローチできる事があります。その際のポイントは以下の6つです。
持ち物選び
- 自分で使える機能的なモノ
- 使い慣れたものをあまり変えない
- サイズは子ども、素材は大人
- 子ども“も”選ぶ(なんでも子どもに決めさせればOKという訳ではない)
子どもが選ぶ機会を増やす
- 最初は2択から
- 大人が全て選ばない
お片付け
- 楽しくする
- 大人がモデルを必示す
- なれるまでは適度に手伝う
- 子どもが管理できる量の玩具にとどめる
気持ちに寄り添う
- 気持ちに共感する
- 不要に褒めない
お手伝い
- はじめての作業は丁寧に見せる
- 見せる事に集中している時は話さない
- お願いしたのに口出ししない
- 多少の失敗には目をつむる
- 感謝する
ダメを伝える
- きっぱりとした態度
- 簡潔に・具体的に・穏やかに
- ポジティブに言い換える
- 態度をコロコロ変えない
子どもの家

「子どもの家」とはモンテッソーリメソッドを考案したマリア・モンテッソーリが開いた教育施設のようなものだと思っていただければいいかなと思います。
そこは、全てが子どもの為に設計された環境である事が求められました。
今でもモンテッソーリメソッドを行う施設は「子どもの家」と呼ばれている事も多いです。
そんな子どもの家の特徴をいかに述べていきます。
子ども同士の関わり方
- 個性の多い友達がいて刺激的である
- 違っているけれど大切な存在である
- 知らない事は友達から吸収する事が出来る
- 友達が知らない事は教えてあげる事が出来る
- 一人では大変な事も協力する事が出来る
子どもの家の環境構成・5つの領域
控え目な教師

モンテッソーリメソッドでは控え目な教師が子どもと生活を共にしていきます。
そしてモンテッソーリ教師には次のような12の心得というものがあります。
- 環境に心を配る
- 教具や物の取り扱い方を明確、性格に示す
- 子どもが交流を持ち始めるまでは積極的に、交流が始まったら消極的にふるまう
- 探し物をしている子どもや助けの必要な子どもの忍耐の限度を見守ってあげる
- 招かれたら応えていく
- 招かれたらよく聞いてあげる
- 子どもの作業を大切にし、中断や質問を避ける
- 間違いを直接的に訂正せずに、間違った子どもを尊重する
- 休んでいる子どもや他人の作業を見ている子どもを無理に呼んだり、作業を押し付けない
- 作業を拒否する子どもや知らない子ども、間違っている子どもには、たゆまず作業に誘い続けてみる
- 探し求める子どもには傍にいる事を感じさせ、見つけた子どもに対しては隠れる
- 作業が済んで快く力を出し切った子どもには沈黙のうちに喜びを感じさせる
モンテッソーリ教具

モンテッソーリメソッドではモンテッソーリ教具と呼ばれる玩具を使用します。
そしてモンテッソーリ教具、及びその使い方には以下のような特徴があります。
- 子どもの家に同じものは1つしかない
- 子どもが取り扱えるサイズ
- 1つの目的の為に作られている
- 子どもが誤りに気付ける
- 美的である
自由時間

モンテッソーリメソッドでは自由時間を
自分を知ったりチャレンジしたり、選択する時間であると位置付けています
縦割りクラス

子どもの家では基本的に縦割りクラスで生活が営まれていきます。その特徴とメリットは以下の通りです。
- 「年下のサポート」
- 見通しが立つ
- 教える事で理解が深まる
- 得意な分野は先に進める
- 人と穴痔で安心という感性は存在しない
モンテッソーリの4期
前提としてモンテッソーリメソッドは幼児教育に特化したものではありません。
対象は0~24歳と幅が広いのも特徴です。そしてその0~24歳を4つの時期に分けて考えます。
モンテッソーリの4期
【第1期】
年齢:0~6歳
変容期:敏感期の作用にともない身体・精神に基本的機能を育てる時期
【第2期】
年齢:6~12歳
一定成長期:広い行動範囲を決める時期、道徳心の誕生、心の抽象化、文化への関心
【第3期】
年齢:12~18歳
変容期:生理的な変化による困難に直面する。正義感や社会性の完成
【第4期】
年齢18~24歳
完成に到達しつつある人格:専門的な探求者。世界に貢献する職を探す時期
学童期

4期の中でいう第2期。これが日本で言う学童期に当たります。では学童期にはどのような関わりが必要なのでしょうか。学童期の特徴をモンテッソーリメソッドの視点でみていきましょう。
第2期の特徴
- 理性が発達し、論理的に考える力が高まる。文化の習得に適する時期
- 道徳観に目覚める。よし悪しを自分ごととして理解したい
- グループで行動するようになる。(リーダーと従う者の存在が生まれる)
モンテッソーリ小学過程プログラム
【教科】
・数学(算数・代数・幾何学)
・地理学(物理・科学を含む)
・言語
・生物学
・歴史
・音楽
【クラス】
1~3年生・4~6年生の縦割りクラス。
【授業】
・自分の興味に応じてグループレッスンを受ける事が出来る。
・論理的思考の敏感期に記憶するだけの勉強はもったいない!
・興味に応じてアクティブラーニングをする。
まとめ
いかがだったでしょうか。この本ではモンテッソーメソッドという言い回しがされていますが、多くの場合は「モンテッソーリ教育」と訳すのが一般的です。
ではなぜ本ではそのような言い方をしなかったのか。
おそらくモンテッソーリ教育が持つ「子どもへの練習・教えこむ」ことがモンテッソーリ教育の核にあると勘違いをして欲しくなかったからではないかと思います。
マリア・モンテッソーリは子どもをよく観察するなかで子どもの興味や関心を大切にし、「モンテッソーリ教育」というものを生み出しました。家庭でモンテッソーリ教具等を使って遊ぶ場合も、「子どもから始める」という本質は見失わないようにしたいですね。
私もこの本を通して、モンテッソーリ教育がどういうものなのかをざっくり知る事が出来たばかりでなく、モンテッソーリ教育へのイメージも変わりました。是非おススメなので気になる方は実際に読んでみてください♪

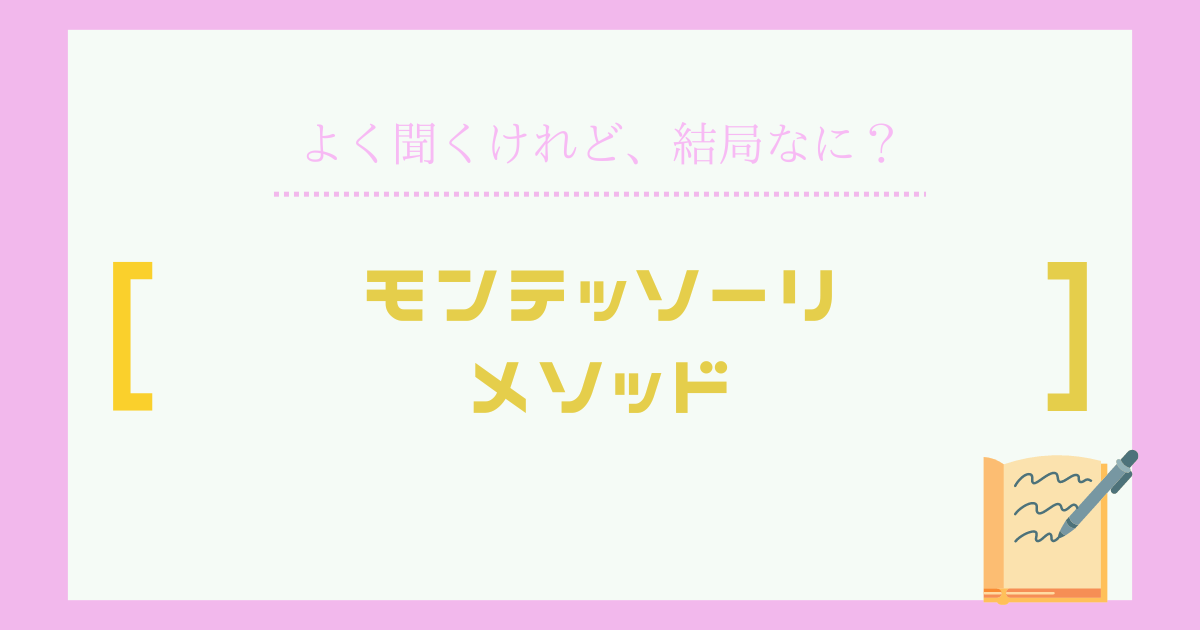
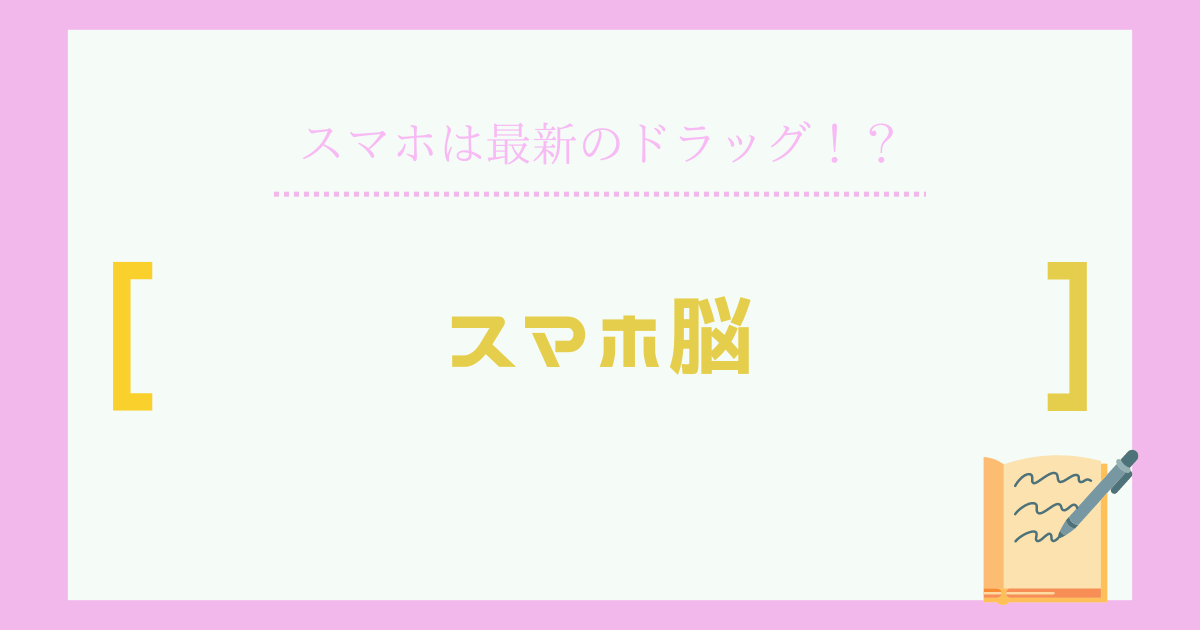
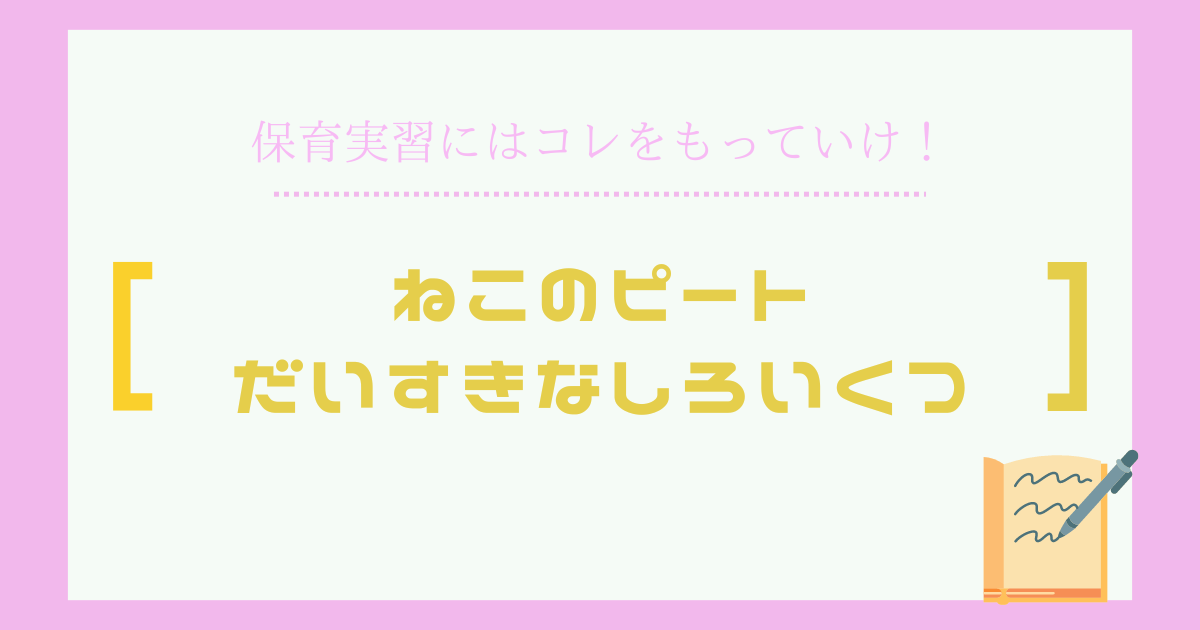
コメント