人間と睡眠
私たちの現在の脳は何万年という進化の過程の中で形成されてきました。この何万年の中で自然や社会の環境は大きく変化してきましたが変わらないものもいくつもあります。その1つが朝に日が昇り、夕方日が沈み夜がくるという太陽のサイクルです。
そのため私たちの脳は太陽が昇ると脳が活性化し、夜寝ることで脳を休ませる(情報を整理する)というサイクル(早起き早寝のサイクル)の中で脳が成長するように遺伝子レベルからつくられています。
睡眠不足がもたらす影響・・・
では夜遅い就寝により睡眠が乱れている場合、どのような脳の影響がでるのでしょうか。
簡単に表すとこんな感じです。

1.睡眠が乱れていると・・・

2.前頭前野の働きが著しく落ちます。
2.ストレスホルモンのノルアドレナリンの分泌が増え、イライラします。
2.神経伝達物質のドーパミンが減少し、ぼーとしたり、やる気がでません。

3.前頭前皮質が働きをとりもどすために、甘いものなど高カロリーのものを摂取するよう指令をだします

1.自律神経が乱れることにより、集中力がない、イライラ・グズグズが増える、夜なかなか寝つけないなど自律神経失調症がおきてきます。結果として更に睡眠が乱れていきます。
睡眠の乱れはすべてが体質という訳ではない!!
以上のように、脳の発達や睡眠の科学的知見からも「早起き早寝」は乳幼児期の「しつけ」として親が子どものために必ず身につけさせておくべき、もっとも優先すべきことです(睡眠の乱れはその子の人生に大きな負の影響をあたえます)。逆に子どもの睡眠リズムは一度身につくと習慣化しやすいので乳幼児期で根気よく頑張ると小学校以降は悩むことはなくなります。
家族で取り組んでいく価値は十分にあると思います!
具体的な目安はあるの?
就学の事まで見据えると、お布団にはいる就寝時間は21時までが理想的です。
大人の決意と工夫で子どもの睡眠リズムはつくれるので、悩まれたらお気軽にコメントやTwitter・InstagramのDMにてご相談ください。
次の記事はコチラ!
最新の科学に基づく躾(しつけ)のコツと考え方! | 保育ふぁん! (hoikufun.com)で紹介してきた躾のコツ。それを踏まえて今回は、睡眠を躾として取り組む事の大切さを再確認してきました。
さて、2つ目の大切にしたい躾の優先事項は歯磨きです。

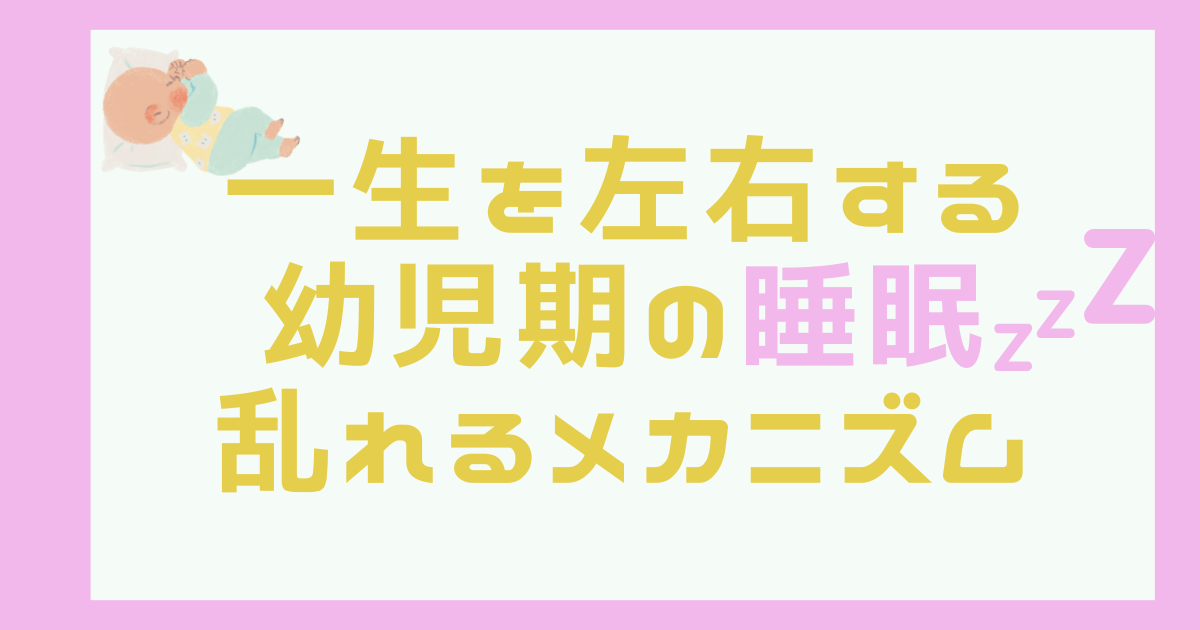
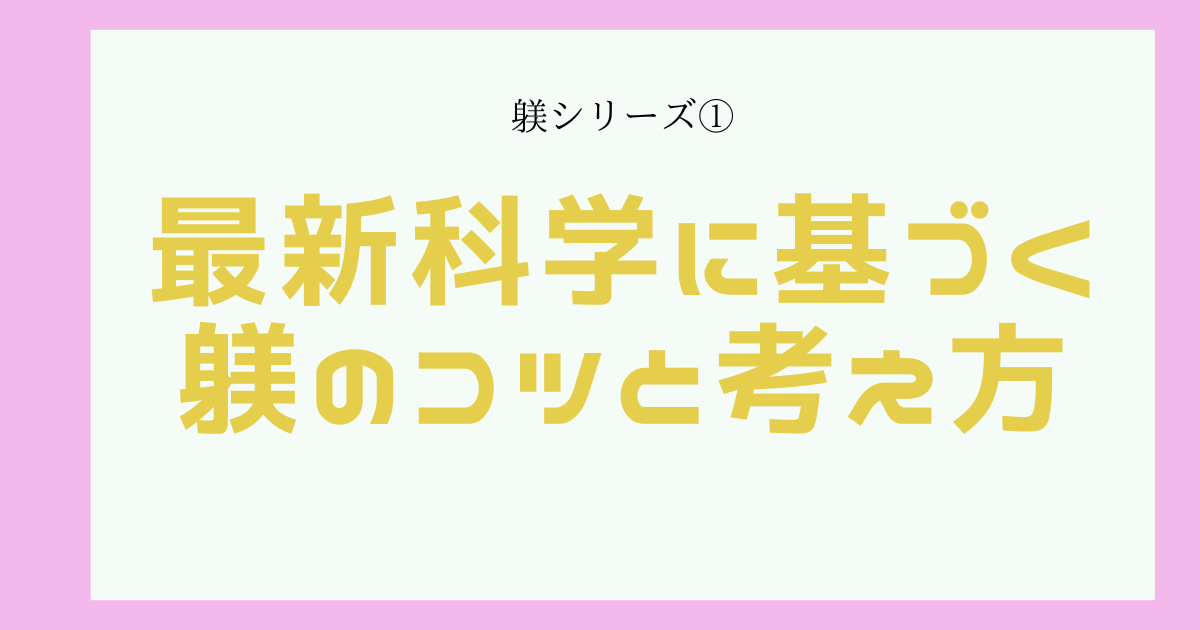

コメント