今回ご紹介したい書籍は佐伯夕利子さんによる『教えないスキル』です。
スペインで最も堅実な育成組織を持つビジャレアルは2014年から人格形成に軸足を置いた指導を追求し始めます。その改革に携わったコーチの1人がこの本の著者です。
・職場で部下を持つ立場にある人
・コーチングに興味のある人
・教育に関わる仕事をしている人
・自分で考えられる子に育てたい親御さん
教えないスキル 概要
コーチングの全てが詰まった1冊。教育現場にも、ビジネスにおける育成場面でも、家庭でも活かせる最強のスキルがこの教えないスキルです。

保育に活かせるノウハウもたくさん出てきます!!
著者:佐伯 夕利子
出版日:2021年2月1日
ページ数:192p
値段:880円(+税)
出版社:小学館
①自分の言動に責任を持つ

ビジャレアルでは改革の為に、コーチにカメラとマイクを付けて行動の分析を行いました。
自分の指導を撮られて分析されるという行為の恥ずかしさや屈辱には共感できる保育士さんも多いでしょう。しかし、ビジャレアルはこれを行いました。
その結果、その声掛けに意図はあるのか?という疑問が浮かびあがってきました。
さらに、習慣化している事や信じてやまない事にあえて(?)を付けてみる事も大切だといいます。
そう、学びなおしには多大な努力が必要となるのです。
本ではこの事について ラーン(学び)⇒ アンラーン(学び壊し) ⇒リラーン(学び直し) という流れで説明されています。
②問いを投げる

問いを意識的に投げる事は、考える癖をつける事へと繋がっていきます。
また、その際には「オープンクエスチョン」を使う事が推奨されています。
オープンクエスチョンとはYES or NOで答えられない質問の事です。
人が成長できる環境づくりの為にも問いを意識的に投げていく事は大切だといえます。
③パフォーマンスを生む言葉を選ぶ

スポーツの業界ではよく、良いね!!!! や ナイス!!!!
という言葉が使われるようですが、本の中ではこれらの言い方は無意味であるとバッサリ!
良いね!やナイス!という言葉から、選手が学べる言葉は何もありません。具体的にどこがどんな風に良かったのかを知る事が次のパフォーマンスへと繋がっていくのです。
ではどうすればいいのか、問いを投げる事です。そしてもう一つコツがあります。それは、教え込まない事です。
人は教え込まれると「自分で考える」脳が休止します。教え込まれた人は「知っている事」しかできません。これでは見える選手にはなれない。大切なのは試合中、自分で考えて行動できる事。これが出来るか否かではゲームのパフォーマンスに大きな差が出ます。
さらに、「良いね!」や「ナイス!」のようにイメージで言葉を選んでも、その伝わり方は当然人それぞれです。コーチが伝えた気になっても実際にはほとんどの場合、伝わっていないのです。フットボールでよく使われる
- 走れていない!
- ボールを動かせ!
- ラインが高い!
等の言葉も曖昧な言葉の仲間。つまり、パフォーマンスを生む言葉とは言い難いものだったのです。
④伸ばしたい相手を知る。

まずは相手を知る事。これがコーチングの基本です。
よく、沈黙=考えていない と勘違いしている人がいます。しかしこれは誤解です。
ビジャレアルのコーチたちは相手を知る為に1対1での対話を大切にしました。その中で、以下の3つの事を意識したそうです
- 主観だけで考える癖をなくした
- 自分の考えを一方的に伝達しない
- 答えに正解はない
これらの事を意識したコミュニケーションで相手を知る事に、ビジャレアルは多くのエネルギーを割きます。
⑤丸テーブルに変える

ビジャレアルではU15が試合の結果やアドバイスをU16に教える場面も多くみられるそうです。
日本では後輩が先輩にレクチャーするなんてなかなかできませんよね。ビジャレアルにはみんなで学び合う。どんな意見も認め合う。という文化が出来上がっているのです。
そしてここでもう一つ、大切な言葉が出てきます。フットボールにおいて、「練習させる」という表現は主語がコーチにある。対して「練習する」という表現は主語が選手にある。この差は大きいものです。
そう、コーチは支配者ではありません。指導者なのです!!
では支配者ではなく、指導者になるためには
- 常識ある範囲で
- 選手を最優先に
- 科学的根拠に基づいて
指導を行う事が大切なんだそうです。
⑥教えないスキルを磨く

ここまで読むと、教えないスキルが何なのか、少しイメージが沸いたのではないでしょうか。さすれば、次は教えないスキルを磨く番です。コーチはこれを磨く努力をしなければなりません。
具体的には、コーチは教えない代わりに心地の良い学びの環境を準備する事が最大の役割です。指導者は潤滑剤(ファシリテーター)であるとの表現もあります。
選手が円滑に学べるサポートをする。これが教えないコーチなのです。
その為には、“教える”という考え方を手放さないといけません。
“教える”は指導者が主語です。これの対義は“学ぶ”です。こちらは選手が主語となります。
⑦認知力を高める

ここまで読んでいただいた皆さんは、新しいリーダーは教えるのではなく、問いを投げる事が大切であると知ったことでしょう。
一方的に知識を教えるのではなく、心地よい学び環境を整える事がリーダーとしての仕事である事も理解して頂いたと思います。
ですが、疑問に思いませんか?
確かに、この方法なら選手が主体的に学ぶ事が出来る。ほんとにこんな指導でサッカーチームは強くなるのか。と
この疑問を解決する鍵が、「認知能力」です。
このような練習を積み重ねたビジャレアルの選手は、試合において一人ひとりが自分で考えて動ける選手です。教えないコーチの元で選手達は自分の頭で考える習慣を習得します。
例えば、ビジャレアルの練習ではたとえ3歳児であっても判断を伴わない練習はしないそうです。
日本のコーチが次に目指すべきは「教えないスキル」
脳内思考のスピード・質の高さ・しなやかさを身につければ日本も上位に食い込める。と著者は言います。これまで「頑張る文化」が強かった日本。みんな頑張る事は大得意です。
考える事を放棄して、頑張るという手段に逃げてしまう事は確かに手軽に満足感を得られるメリットはありますが、そんな小手先の技が通用する時代は終わったのです。
それはサッカーに限った話ではありません。あらゆるスポーツやビジネスにおいても同じ事が言えます。
これからは「頑張る文化」ではなく、「創造する文化」の時代です。
生きやすいけれど息苦しい日本。
コーチングする立場にある人は、新しい時代に有効なアプローチ教えないスキル。是非学んでいきましょう
気になった方は是非この本手に取ってみてください。



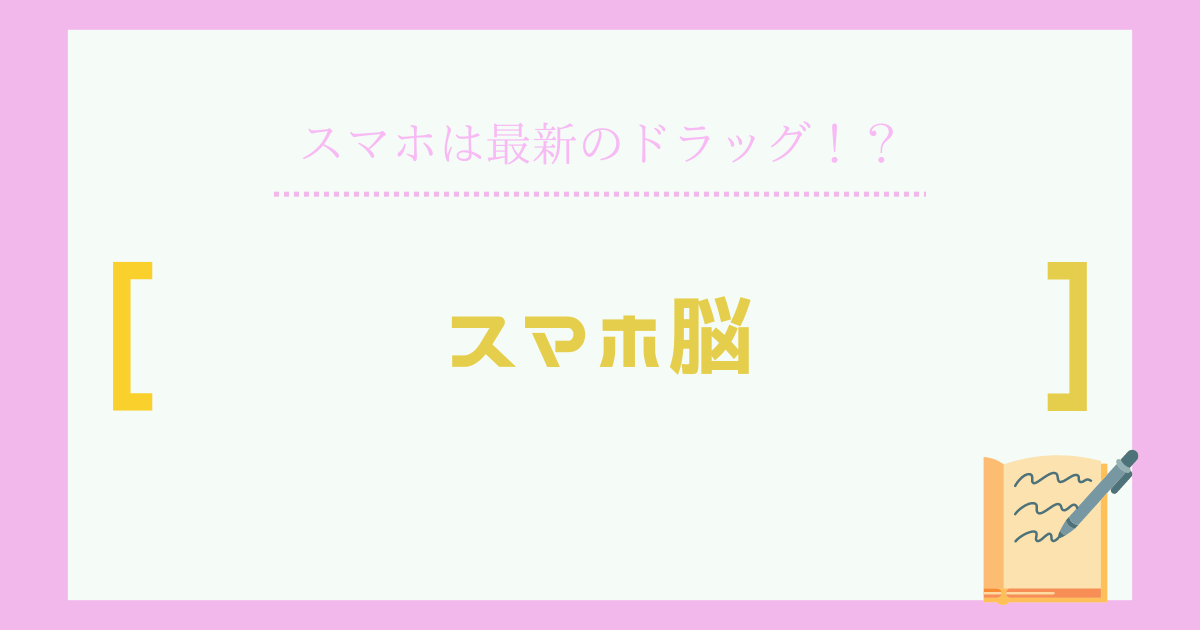
コメント