知的障がい・肢体不自由・自閉症スペクトラムなどの障がいのある子どもは、
- 話相手の意図が理解できない
- 自分の意見を相手に伝えられない
- その他コミュニケーション上の問題がある
これらの特徴がある場合があります。
こういった子どもは日常生活上の困難にぶつかる事があります。これはもともとの障害とは別にコミュニケーション障がいを併発している可能性があります。
関わり方の注意点
こういったコミュニケーションの障がいは言語の発達と大きくかかわっています。
しかし、言語の発達には大きな個人差があります。
たとえば、地域・文化的背景・時代的背景によっても異なります。
つまり、コミュニケーション障がいは様々な要因を配慮すべき相対的なモノなのです。
コミュニケーション障がいには、どんな特徴のものがあるのか
発語の誤り
【省略】
・本来発音されるべき音の省略をしてしまう。
例)ひこうき⇒コーキ
【置換】
・特定の音が他の音と変わる
例)ラッパ⇒ダッパ
【歪み】
・明らかに誤りだが、カタカナ文字で表記しにくい発音
【付加】
・他の音を加えてしまう
例)サラダ⇒オサラダ
構音障がい
子どもがその音を作れず、語音を誤る状態の事。
構音(様々な音を作り出す事)は、筋肉・発音・発語器官等の複雑で協調的な運動によって作りだされる高度な活動です。
ここで大切なのは「語音の誤りは発声・発語器官の一時的な機能不全」とも考えられている事です。
つまり、発達が進むにつれて改善する場合もあるし、聴覚弁別力(音を聞き分ける力)の発達によって改善する場合もあります。
しかし、構音障がいの背景には複雑な他の問題がある場合も多く、慎重に検討したうえで場合によっては早めの指導が必要な場合がある事も覚えておきましょう。
また、器質的異常の有無により、器質的構音障がいと、機能的構音障がいに分類する場合もあります。
発音獲得の目安
ここで発音獲得の目安を確認しておきましょう。
前提としてこれは目安であって必ずではない事をしっかりと理解しておく必要があります。
【2~3歳】
- あ行
- た・て・と
- ぱ行
- ま行
- や行
- ん
【3~4歳】
- か行
- が行
- な行
- ち・ちゃ・だ・で・ど・わ
- は行
- さ行(特に難しい)
※構音障がいは口腔外科に相談したり、就学前検診で発覚する場合も多い障がいです。このような発音の発達から意識的に見つけてあげる事が出来れば必然的にアプローチも早くなります。
音韻障がい
ある時には語音を発音できるのに、別の場面では正しく発音できない障がいです。
流暢性障がい
吃音と早口症が代表的です。話言葉が途切れる、スピードが不自然である等を特徴とします。
特に吃音では
- 「ぼぼぼぼ僕ね」といった語頭音の繰り返しを連発する。
- 「ぼ~くね」といった語頭音の引き延ばし
- 「“ ”ぼくね」といった語頭音のブロック(詰まってでない)といった特徴がある
また症状の重い場合、発語に伴ってまばたきをしたり、手足で調子を整えるといった特徴もあります。
早口症では、話す速度が速い為に不自然な箇所で区切ったり間を置いたり、随伴症状が出現する場合もあります。
発音障がい
- 声の高さ・低さ・質に障がいが見られる場合
- 声が高すぎる or 声が低すぎる・単調すぎる・大きすぎる or 小さすぎるなど
- 質の障がいは、カスレ・しわがれ声・鼻声等がある。
言語障がい
言語の5つの次元
- 音韻論
- 形態論
- 統語論
- 意味論
- 語用論
のいずれかもしくは、いくつかに障がいを示すものを指します
また、言語障がいは以下の2つに分類される事もあります。
- 受容性言語障がい(これは理解の障がいです)
この子どもは、話言葉が理解できず、指示に従えない等の特徴がある
- 表出性言語障がい(これは表出の障がいです)
この子どもは、語彙数が少ない、誤った単語や語句を使う。身振りでしか意思
伝達できない等の特徴がある。
※臨床的には両者に障がいを持っている場合が多いと言われています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
特徴にあてはまる子どもがクラスにいるという保育士さんもいるのではないでしょうか。知識がないとあまりピンとこないコミュニケーション障がいですが、その特徴をしっかり押さえて、可能性を吟味する事も大切かなと思います。
特に、別の障がいと併発しているケースは見落とされがちなので注意が必要ですね。

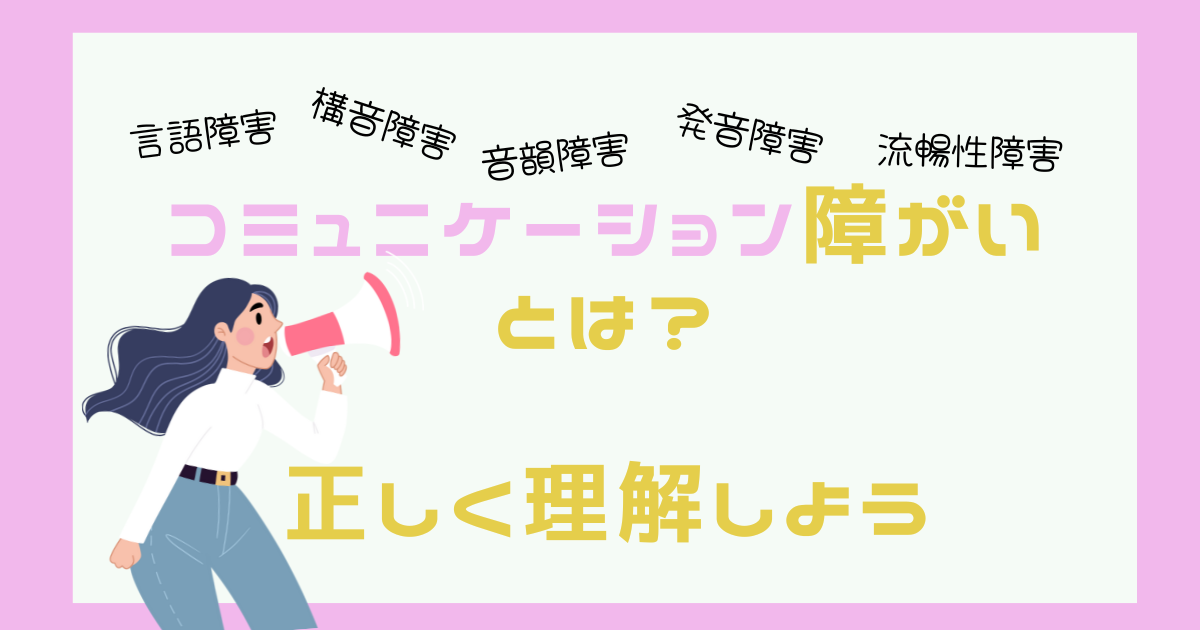


コメント