皆さんも疑問に思った事があるのではないでしょうか。
あの子と私、同じ勉強をしているのになぜ差がつくの!?
そんな人類が長年抱き続けてきた大きな疑問を解決してくれる素晴らしい本がこちらです↓
教育に関わる全ての人が理解しておきたい、同じ勉強をしているのに「デキる子」と「デキない子」が存在するメカニズムを分かり易く紹介してくれています。
・子どもに勉強を楽しんで欲しい
・自己啓発をしていきたい
・自分の頭で考える子どもを育てたい
私はこの本を読んで自分の言葉掛けを改めて見直す事が出来、保育中の言葉のバリエーションが格段に増えました。
特に以上児の担任の先生には就学後を見据えるという意味も込めて、是非手にとって学んでいただきたいと思います。
同じ勉強をしていて、何故差がつくのか の概要
著者、石田 勝紀さんは (一社)教育デザインラボの代表理事を務める、バリバリの教育マンだ。
そのうえで、Yahoo!ニュース公式コメンテーターやVoicyのパーソナリティをを務める等、その考えを広める活動も多く行っています。

本書はそんな著者が、「東洋経済オンライン」で265万ものPVを記録し、大反響となった伝説の記事を書籍化したものになります!!
著者 : 石田 勝紀
出版日 :2020/2/21
ページ数:351p
値段 :1500円(+税)
出版社 :ディスカヴァー・トゥエンティワン
同じ勉強をしていて差が付く謎の答え
本書の結論から言うと、同じ勉強をしているのに差が付くのはズバリ考える力の差だそうです。
この本では、学びのタイプを3つに分けています。それが以下の通り
- 学んでいるように見えるが、学ぼうと思っていない人
- 授業中、仕事中にしか学ばない事
- 日常生活全てが学びになっている人
当然、①と②の人は③の人に勝てません。③が最強です!!
そう、同じ勉強でより深い学びを得る為には日常生活が全て学びであるという感覚が必要になります。
東大生の特徴
“デキる人”とは何だろう。そんな疑問を解決する為に著者は東大生にヒヤリング調査を行いました。その中で、東大生には3つの共通点がある事を発見します。それは…
- ボキャブラリーが豊富(説明力がある)
- 集中して人のはなしを聞く(集中力)
- 自らの意見を語る(考える力)
こういう人達はまさに、日常生活全てが学びになっている人達です。
勉強は生活の一部であり。友達との会話も授業中のやり取りも、本質は同じ事!
気づき ⇒ 知り ⇒ 考える
という習慣を生活の中に取り入れて、続けていく事で脳の構造から変わっていくそうです。
やはり、キーワードは考える力なんですよね
考える状態になるには?
同じ勉強で差が付く理由が考える力にあるというが本書の結論でした。
では、考える状態になるにはどうすればいいのでしょうか。
本の中では2つのアプローチが提案されています。それは
アプローチ①「疑問をも持たせる」
アプローチ②「まとめさせる」
疑問を持たせる
疑問を持つようになるためには、
- 原因分析力
- 自己表現力
- 問題解決力
の3つのスキルが必須になってきます。
その為、大人はこの3つのスキルを育む関わりをしていく必要があります。
まとめさせる
まとめる為には
- 抽象化思考力
- 具体的思考力
の2つのスキルが必須になります。
その為、大人はこの2つのスキルを育む関わりをしていく必要があります。
その他の補強スキル
上記5つのスキルに加えて、
- 積極的思考力
- 目的意識力
- 原点回帰力
- 仮説構築力
- 問題認識力
の5つの補助的なスキルもあると尚良いそうです。
10のマジックワード
上のブロックでは、考える力を育てる為には、
- 原因分析力
- 自己表現力
- 問題解決力
- 抽象化思考力
- 具体化思考力
- 積極的思考力
- 目的意識力
- 原点回帰力
- 仮説構築力
- 問題認識力
の10のスキルを育むが必須であると記してきました。
しかし、著者は言います。これ、ぶっちゃけ難しくない!?と
「大げさに表現しても、どこか他人事になってしまう。それなら、シンプルに表現してしまおう!」
というのが著者の考え方です。そのため、著者はこの10のスキルを育む10のマジックワードというものを提案してくれます。それが、
- なぜだろう
- どう思う?
- どうしたらいい?
- 要するに?
- 例えば、どういう事?
- 楽しむには?
- 何の為?
- そもそもどういう事?
- もしも~。どうする?どうなる?
- 本当だろうか
の10の言葉です。
本の中では、この言葉たちについて詳しく解説してありますので、是非本を読んでその意図を理解してから、言葉を掛けていく方がいいかなと個人的には思います。
まとめ
同じ勉強をしていても差が付く理由と対策
⇒出来る人は日常生活全てが学びになっている
⇒そんな人達は、考える力が違う。
⇒考える力はアプローチでバージョンアップする
⇒そのためには10のマジックワードを使え!
いかがでしたか?
同じ勉強をしているのに、学びが深まる子どもとそうでない子どもがいる事は事実です。今回はそのメカニズムと具体的なアプローチ方法の書いてある本を紹介しました。
私自身は幼児教育の現場に従事していますが、この様な問いかけやマジックワードは年齢や場面に応じて積極的に使っていこうと思います。
私も、もともとは勉強が出来る方ではなかったので、「同じ勉強をしているはずなのに開いていく友達との“差”」に確かな恐怖や悔しさを覚えた時がありました。しかしそんな経験があるからこそ、子ども達には「勉強の楽しさ」に早く気づいて、日常生活の中にある学び事楽しんで欲しいと思います。
今回の本はそんな思いを実現する為にとてもいいバイブルになりました。学童期の子どもを持つ保護者様はもちろん、幼児教育に携わる方へもおススメの出来る1冊です!
また、この記事を読んでいて感じ取った人もいるかも知れませんが、この著者、伝え方がとっても上手で本もすごくかみ砕いて書かれており、分かり易く、読みやすくなっていますので普段読書はしない!という人でも割と読みやすくなっていると思います。もっと詳しく知りたいと思った方は是非手に取ってみてください。

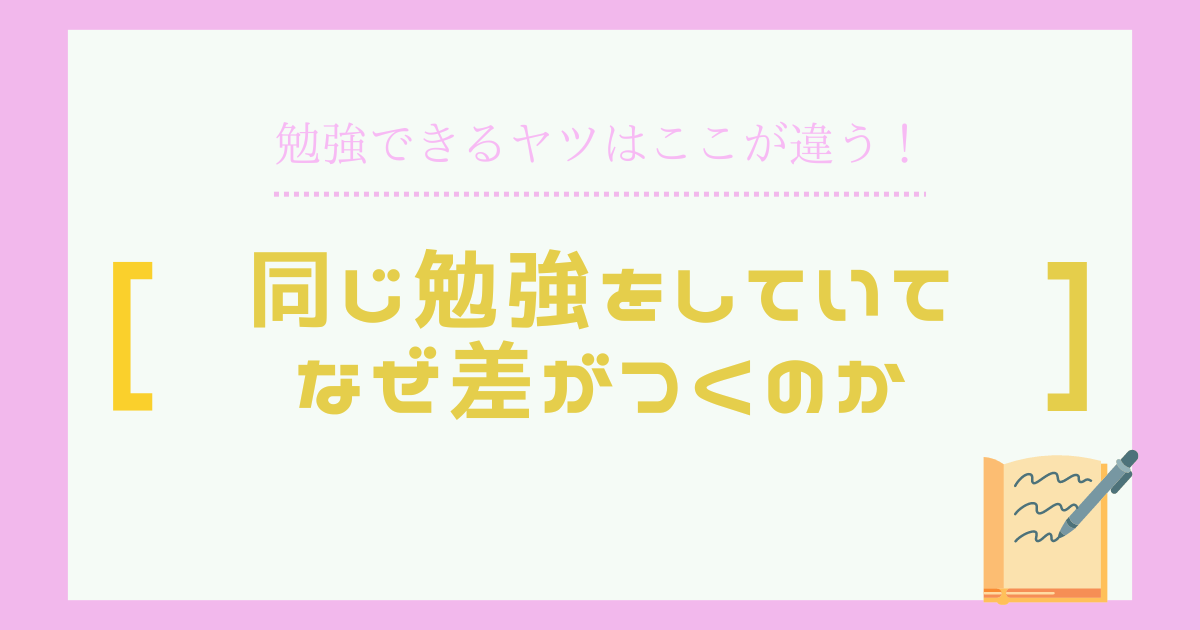
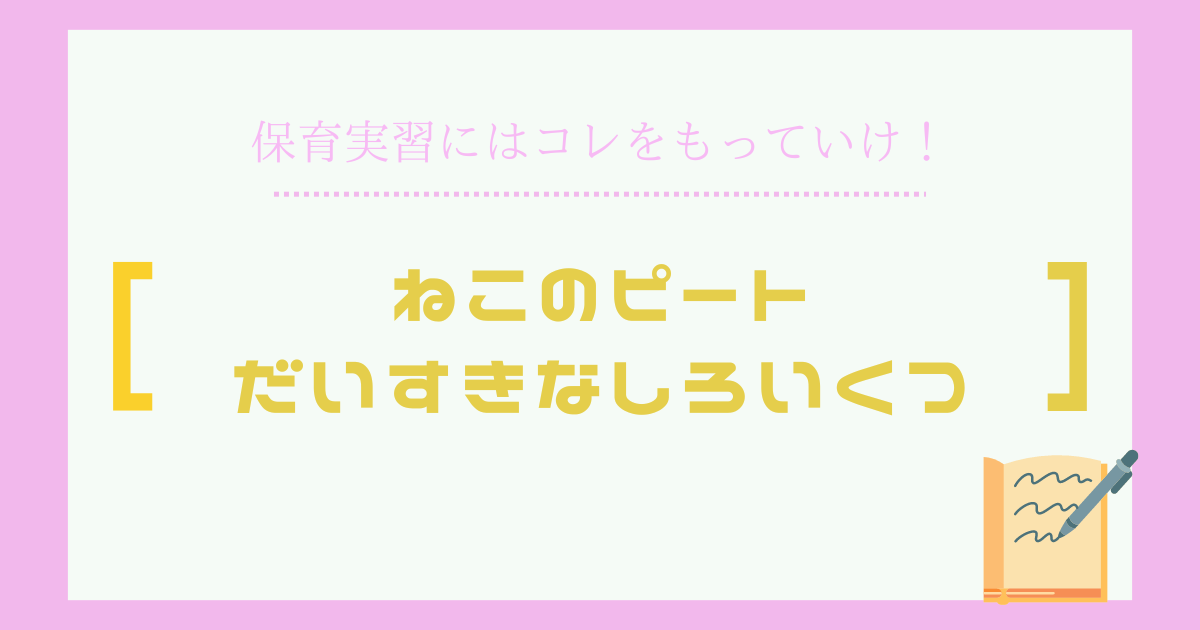
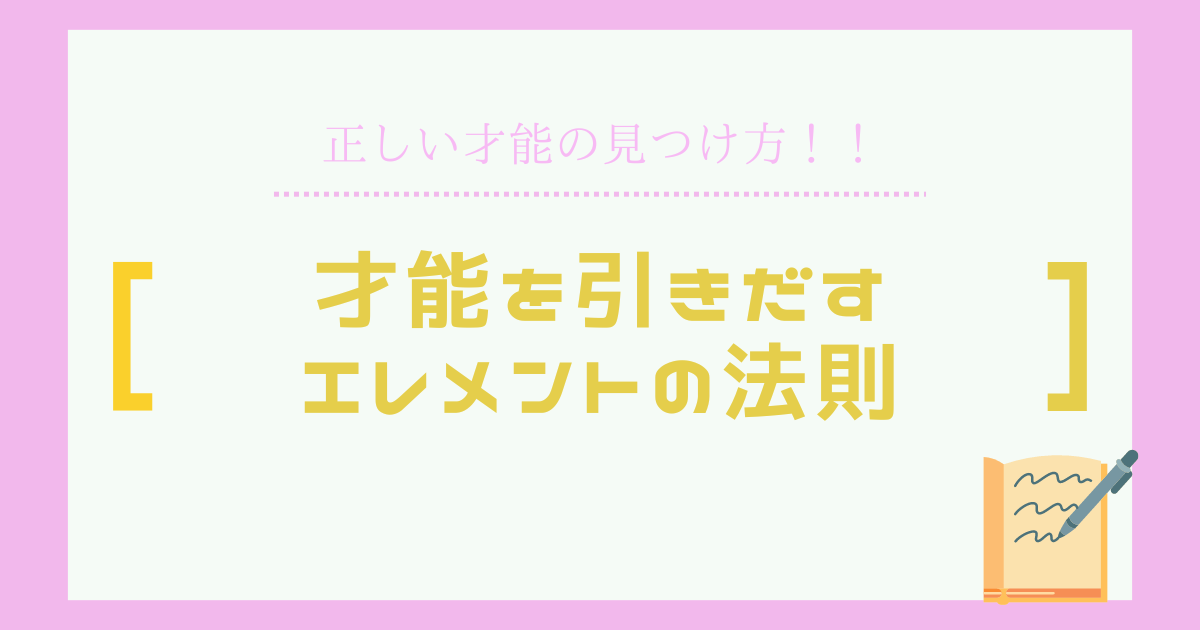
コメント